活動・団体の紹介
特定非営利活動法人 地域で子どもを育む会
2021年に子どもたちのために、大人のできることをするために発足いたしました。2022年に特定非営利活動法人地域で子どもを育む会(NPO法人)神奈川県知事より認定を受けました。
主な活動内容:子どもの健全育成・地域安全・保健・医療又は福祉の増進を図る活動・学術/文化/芸術又はスポーツの振興を図る活動を行っております。
具体的には、寺子屋(学習補習)・子ども食堂(食育)・音楽/芸術など(音楽体験や鑑賞、工作、花育など)・居場所(何かをしなくてもいることのできる安心安全な居場所)を行っております。

活動の背景、社会課題について
2020年より世界的に始まった「新型コロナウイルス」は、同年3月には全国の公立小中学校が休校となり、それから3年間、コミュニケーションを自由に取れない状況が続き様々な影響が出ました。子どもにとっての1年はとても長く、成長への懸念が心配されました。
子どもたちが安心して過ごせ心のよりどころとなる居場所、また、年齢や考えかとの違う人とかかわる中で、社会での自分の立ち位置や人とのつながりを学ぶ居場所が必要でした。

1. 教育への影響(学習の遅れ・オンライン授業)
感染拡大防止のため、学校が長期間休校になったり、オンライン授業が導入されたことで、以下のような問題が起きました:
- 学習の理解度に差が出る(特にサポートの難しい家庭の子ども)
- オンライン環境が整っていない家庭では、授業に参加できないことも
- 友達との交流が減り、学校生活へのモチベーション低下
2. 心の健康への影響(孤独・不安・ストレス)
外出自粛やイベント中止により、子どもたちは普段の遊びや人間関係の中での「心の栄養」を得られにくくなりました:
- 孤独感や不安感の増加
- 家庭内のストレスが子どもにも影響
- 思春期の子どもでは、将来への不安やうつ傾向が強まるケースも
活動内容の詳細、実績について
2022年7月より、週一回夕方から夜にかけて居場所、寺子屋&子ども食堂を開校。
◆ 居場所の主な活動内容
1. 居場所
- 自由な居場所(何もしなくてもOK)
- 多世代の居場所(小1~中学、高校生、大学生、大学院生、社会人、70代までの大人ボランティア)
- 安心して過ごせる居場所

2. 学習支援(宿題・勉強の手伝い)
- 学校の宿題や、わからないところの個別サポート
- 教科にこだわらず、「学ぶ楽しさ」を大切にする
- 苦手意識をなくし、少しずつ自信をつけていく

3. 遊びや交流の時間(花育・音楽など)
- 外遊びやボードゲーム、手作り工作などを通じた自由な時間
- 年齢の違う子どもや地域の大人と交流し、温かな関係を築く
- 近隣音楽大学の先生や学生による音楽体験や演奏会などで自己肯定感を上げる
- 生花を使い「花育」で情操教育

4. 食事・おやつの提供(必要に応じて)
- 自分で握る「おにぎり講習」、おやつの提供を通して、心と体を満たす
- 一緒に食べることで会話が生まれ、安心感につながる
- 近隣の管理栄養学科に在籍する学生の皆さんによる「食育」活動
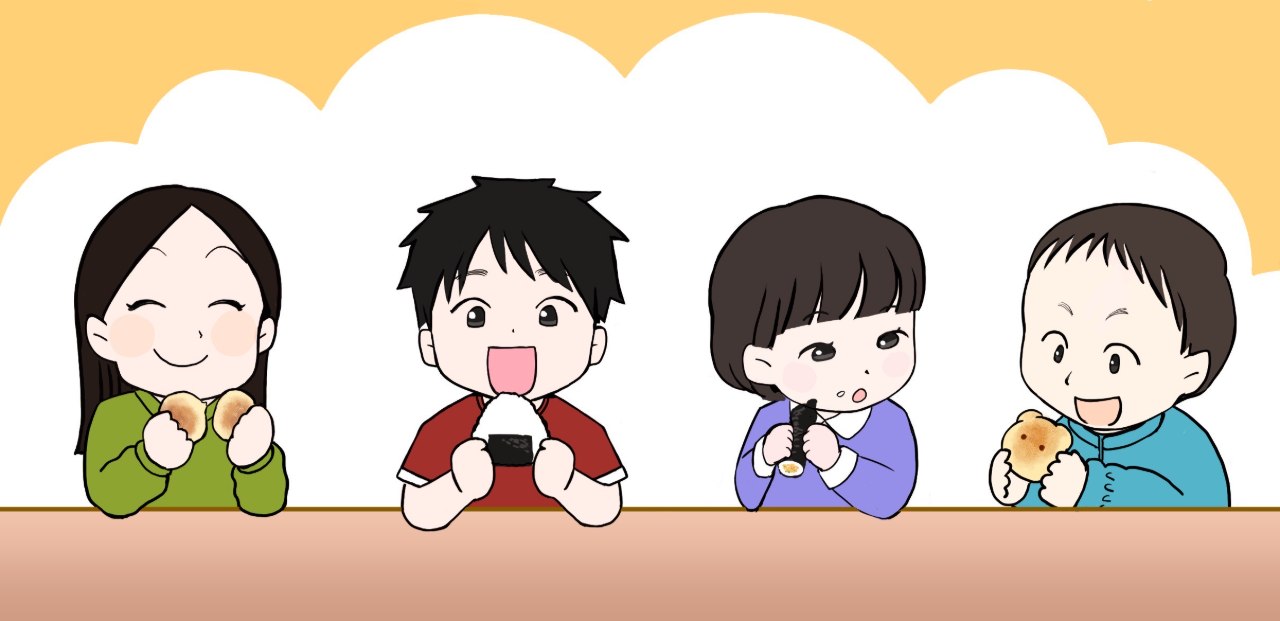
◆ 実績
- 2022年 参加延べ人数 45名(小学生)15名(中学生)3名(高校生)10名(大学生)10名(フリーター)9名(社会人)82名(大人)
- 2023年 参加延べ人数 645名(小学生)112名(高校生)96名(大学生)17名(社会人)258名(大人)
- 2024年 参加延べ人数 840名(小学生)54名(中学生)128名(高校生)66名(大学生)12名(社会人)250名(大人)
- 子どもの出席は自由となっておりますが、出席率は98%以上。風邪などでお休み以外は全員出席しています。

- 川崎市民公益活動助成(2022年・2024年)ソニー子ども音楽基金(2023年)子どもの貧困に立ち向かう市民活動助成(2024年)地域の学びの場助成(2024年)内閣官房地域における孤独・孤立対策に関するNPO等の取り組みモデル調査研究業務事業(2023年・2024年)
代表者メッセージ

子どもたちの未来を、地域みんなで守り育てるために
はじめまして。NPO法人地域で子どもを育む会 代表の小畑です。
この活動は、コロナ禍で急激に変化した子どもたちの学びと居場所の環境に、強い危機感を抱いたことから始まりました。
「誰かが動かなくては、このままでは子どもたちが取り残されてしまう。」
そんな想いで、私たちは立ち上がりました。
前職では、公立小学校で英語の授業をサポートする立場にありました。
2021年、感染対策で距離を保った授業の中、高学年のクラスの3分の1が授業についていけていない現実を目の当たりにしました。
「この子たちは、どこで学び直せるんだろう?」
「放課後、先生に聞く時間もない。塾に通っていない子は、学ぶ場が他にないのでは?」
そう感じたとき、これはやがて不登校や引きこもりにつながる“未来の分かれ道”なのだと気づきました。
私自身が疑問に思ったことを周囲の方に聞いてみると、ママ友だけでなく、子どもがいない方からも「同じように感じていた」という声を多くいただきました。
そこで生まれたのが、「地域の子どもは、地域の大人で育てよう」という想いです。
私たちが目指しているのは、ただの学習支援や食事提供ではありません。
一緒に過ごし、関わり合い、信頼関係を育てながら、その子の将来を一緒に見守っていくことです。
勉強が遅れ始めると、自信を失い、自己肯定感が下がってしまう。
そんなときに「ここに来れば安心できる」「話を聞いてもらえる」と感じられる場所が、どれほど心の支えになるか。
だからこそ、誰でも来られるように「無料」にこだわって運営しています。
有料にすれば、来られない子どもが必ず出てしまうからです。
今、私たちはまだまだ小さな力です。けれど、子どもたちの未来を諦めたくありません。
この想いに共感してくださる方がいたら、どうか力を貸してください。
もし時間に余裕があれば、ぜひボランティアとして。
難しい方は、ご寄付というかたちでの応援も、子どもたちの大きな支えになります。
地域の未来を、子どもたちの笑顔からつくっていきたい。
どうか、一緒にその一歩を踏み出していただけたら嬉しいです。
応援、よろしくお願いいたします。
寄付金の使い道について

年間合計費用として、約100万円を運営していくうえで必要です。寄付は、、、
1 家庭の経済状況によって、学習や生活の機会に大きな差が生まれています。
- 経済的に困っている家庭の子どもに教材や食事を届ける
-
塾や習い事に通えない子に学習支援の機会を提供する
など、「スタートラインの格差」を少しでも埋める力になります。
2 地域の子ども食堂や放課後の学習支援、見守り活動などは、多くが寄付やボランティアによって支えられています。
- 家庭や学校以外にも、自分らしくいられる居場所を提供
-
食事や会話を通して、子どもが心を開ける時間をつくる
寄付は、こうした大切な場を継続して運営するための支えになります。
3 子どもたちは、社会の未来そのもの。
- 教育や支援を受けた子どもたちは、やがて社会に貢献する存在に
-
一人ひとりの成長が、地域全体・社会全体の活力につながる
寄付は「困っている子を助ける」だけでなく、「よりよい未来をつくる行動」でもあります。




