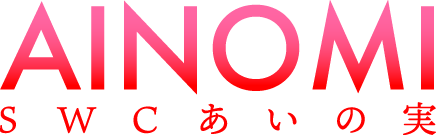「カフェ・ドゥ・チルミル」がつなぐ医療的ケア児者と地域
「カフェ・ドゥ・チルミル」は、2024年4月に仙台市泉区でオープンした、医療的ケア児者の家族を支援するためのカフェです。社会福祉法人あいの実が推進する「仙台あばいんプロジェクト」の一環として設立されました。このカフェは、医療的ケア児者の家庭が抱える就労の難しさや孤立といった課題を解決し、地域社会との自然な交流を生み出すことを目的としています。
医療的ケア児者とは、人工呼吸器や経管栄養などの介護が日常的に必要な方たちを指します。ケアは24時間体制で行われることが多いため、特に母親が就労や社会参加を諦めざるを得ない状況が広がっています。 カフェ・ドゥ・チルミルは、母親の就労と社会参加の機会を実際に提供しながら、課題や解決策を明らかにする先駆的な事業として注目されています。カフェのコンセプトは「アウトドアの体験」です。訪れた方は、コーヒー豆の焙煎やホットサンド作りを楽しめます。アウトドアの体験を店舗コンセプトに据える大きなメリットは、スタッフのオペレーションが調理よりも体験のアシスト中心になることです。これで働きたい母親たちの資格や経験のハードルが下がりました。資金調達では、2023年に実施されたクラウドファンディングにより406万5,000円を調達し、223名の支援者がプロジェクトに参加しました。また、一柳ウェルビーイングライフ基金の助成金や、エペイオスジャパン株式会社からのドリップケトルなどのご寄贈により、円滑なオープンが実現しました。店名のチルミルのチルは、「くつろぐ」、ミルは「コーヒー豆を挽く」ことを意味しています。医療的ケア児者を抱えるご家族も気軽に来店されることが多く、重い障がいを抱えたご家族が地域社会に溶け込み、地域住民が自然に課題を意識する機会となっています。

医療的ケア児者ファミリーが直面する課題と解決の糸口
全国には約2万人の医療的ケア児者がいるとされており、24時間命をつなぐためのケアが求められるため、特に母親の自由が大きく制限されます。宮城県内には約600人の医療的ケア児者がいるとされていますが、子どもを預けられる保育園やデイサービスの受け入れ枠が不足している状況です。子どもの預け先に加え、緊急時に対応可能な労働環境を整えた職場が少ないことが大きな課題です。ある母親は「子どもの学校送迎等で早い時間帯から働くことができない、10:00以降就業開始の仕事が見つからず、退勤についても希望時間が通ることが難しい」と述べました。また、「親の所得に応じたサービス利用料の変化や手当の停止等をなくして、子どもに対して平等に一律にして欲しい。働いて負担分をカバーしたいが勤務先の理解を得るのが難しいから」という声もあります。医療的ケア児者に対する理解の不足が、母親たちの社会参加をさらに困難にしています。私たちあいの実は、2023年に医療型ショートステイ(10床)を開設し、医療的ケア児者を受け入れる体制を整えました。施設に併設されたカフェ・ドゥ・チルミルは、母親たちが経済的な安定を得るだけでなく、生きがいとライフプランを再構築する場としても機能しています。カフェで社会復帰を果たした5人の母親の年齢は38歳~56歳であり、再就職までのブランクは6年~30年です。医療的ケア児者の母親たちが働く姿は、子どもを預けて働くという当たり前の選択肢を彼女たち自身が持つことの重要性を示しています。また、医療的ケア児者の母親も地域社会の一員として働けることを証明し、支え合いの意識を地域に広げる役割を果たしています。

「カフェ・ドゥ・チルミル」の運営体制と勤務のしくみ
カフェ・ドゥ・チルミルの運営体制は、企業との連携、ファンドレイジングによる資金調達、地域住民の理解と参加に支えられています。2024年6月に開催された「現代国際巨匠絵画展-カフェ応援チャリティ~どのファミリーも取りこぼされない仙台へ~」はその一環です。ご支援を頂くと共に、後援団体やボランティアとの連携により、オープンしたてのカフェ・ドゥ・チルミルや、医療的ケア児者とそのご家族の課題を地域に周知する機会となりました。カフェ・ドゥ・チルミルの実施体制においては、母親たちが安心して働けるよう、人員配置や勤務シフトに工夫が凝らされています。現在5人の医療的ケア児者の母親がパート勤務しており、勤務時間は、一人あたり平均56h/月です。スタッフとして働く母親は、個々の家庭状況やサービス利用時間に合わせた柔軟な勤務時間が設定されています。勤務時間中に子どもに緊急のケアが必要となった場合に備え、母親は常時電話を携帯しています。バックアップ体制として、母親たちの急な欠勤に備えて数名のサポートスタッフが待機しています。また、スタッフが必要な休暇を取りやすいように、勤務シフトは週単位で更新されます。スタッフとの円滑なコミュニケーションにより、マネージャーが母親と子どもの体調を常に把握していることが、無理のないシフト調整につながっています。カフェの隣接施設では医療的ケア児者の預かりが可能です。預かり施設では、専門スタッフによる医療的ケアが提供され、カフェと施設間での情報共有もスムーズに行われています。この仕組みが、働きやすさの向上に寄与しています。

働くママたちの声:「カフェ」で得た希望と課題
長期間、育児や医療的ケアに専念していた母親たちは、カフェでの就労を通じて「母親」だけでなく「働く個人」としての自分を再発見することができたと語っています。彼女たちの声をご紹介します。
「子どもや自分の体調不良等の休みや早退でもお互い様といえる雰囲気に救われる」「似た境遇のカフェスタッフ同士での情報の共有や共感が、とても良い」 「近所の方が病児を持ったことをきっかけに、話しかけてくれるようになった。辛い思いを吐き出せる場に自分がなれることに喜びを感じる」「介護疲れのお客様や、同じ境遇の子を持つお客様の話を聞く時に、自分が聞いてもらう側ではなく聞く側に立場が変わり、人の役に立つことができていると思える」「医療的ケア児を持つお母さんたちが、社会資源を利用して子どもを見ないことに関し、罪悪感を感じないで欲しい」「障がいを持った子がいても、やりたいことをあきらめずに挑戦して欲しい」「フルタイムで働ける環境づくりが広がって欲しい」
一方で、家庭と仕事の両立は依然として大きな課題です。子どもの体調次第で勤務を急にキャンセルしなければならないこともあり、スタッフの一人は「家族全体での調整が必要で、申し訳なく感じることもある」と語っています。さらに、医療的ケア児者の家族に対する社会的理解の不足も母親たちの心理的負担となっています。時には不適切な質問や偏見に直面することもありますが、カフェでの経験を通じて地域住民に医療的ケア児者の家族について知ってもらう機会が増えています。
応援企業や団体の声:ファミリーの課題を地域課題へ
カフェ・ドゥ・チルミルのオープニングセレモニーや、カフェ応援チャリティ絵画展では、多くの方から先進的な取り組みに対するエールが寄せられました。一部抜粋をご紹介します。
公益財団法人パブリックリソース財団 代表理事・理事長 久住剛様より:
「医ケア児ママの働くカフェ/カフェ・ドゥ・チルミル」の開設につきましては、公益財団法人パブリックリソース財団「一柳ウェルビーイングライフ基金」の第一回助成の対象として、応援させていただいております。社会福祉法人あいの実は、これまでも医療的ケア児及びその家族への支援に精力的に取り組んでこられました。このたびの「医ケア児ママの働くカフェ/カフェ・ドゥ・チルミル」は、これまでの現場での経験を踏まえて、医療的ケア児を育てるお母様たちに安心して働ける機会を提供する場であり、温かくかつ先進的な取り組みです。今後、このカフェの実践が基礎となって、地域の他の企業等においても医療的ケア児を育てるお母様たちの働く場が広がっていくこと、お母様たちと子どもさんたちの笑顔とウェルビーイングの向上につながることを切に願っております。
株式会社EPEIOS JAPAN 金成賛会長より:
ここまでの出会いの中で、医ケア児ママやパパをはじめ、ご家族の皆さまの毎日の奮闘を見聞し、自分自身も一家庭子供を持つ親として心を揺さぶられました。そしてその大切な出会いから、ケトルの贈呈に辿り着きました。今回オープンのカフェでは、初めて社会参加されるママスタッフの皆さまが、オープン準備での研修でこれらケトルを使って実践経験をされてとても美味しいコーヒーを楽しむことができると聞いています。EPEIOSの企業理念でもある "心も豊かになる製品"を、まさしく現場で使って頂けること、こんな幸せなことはありませんし、働くママさんたちにもご来店されるお客様にも、心を豊かになっていただけたら、二重三重の喜びです。ママスタッフの皆さん、お母さん一人ではないこと、あいの実の皆さま、我々EPEIOSもみなさんと一緒に伴走します。
仙台青葉学院大学看護学部看護学科教授 髙橋由美様より:
先日カフェに伺いまして、香り豊かでおいしいコーヒーをいただきました。 また、ゆっくりお邪魔したいと思います。 わたくしは2年程前、本学の大学移行の準備をしている際に「あいの実」様のご活躍を知る機会がございました。ホームページからは、医療的ケア児やご家族を支えるためのハートフルな取り組みが伝わり、いつか地域・在宅看護の実習をお願いしたという想いにつながりました。 ある日、医療的ケア児のお母さんが 「働く」カフェを建てるクラウドファンディングの情報が目にとまりました。大変感銘を受けまして、直ぐに参加させていただきましたし、仲間にも声を掛けました。 地域・在宅看護を教えるものとして、特にこの十数年は、実習先で医療的ケア児とご家族から学ばせていただく機会が多くなってまいりました。お子さんとご家族があたりまえに生きることを支える仕組みづくりが必要なことは理解していても、実際に行動に移すという発想には至っておりませんでした。ですからほんの少しでも 「あいの実」様の取り組みに参加できたこと、この出会いに心から感謝を申し上げる次第でございます。
医療的ケア児者ファミリー支援の可能性
2023年に実施したクラウドファンディングとチャリティ絵画展では、多くの支援をいただき、カフェのスタートアップを成功させました。次なる課題は、持続可能な運営体制の確立です。医療的ケア児者や母親に配慮した設備、スタッフの研修、イベント運営には特別なコストが発生するため、安定した収益を生み出す仕組みが必要です。そのため、メニューの多様化や魅力的なイベントの定期開催を通じ、収益構造の見直しを進めます。また、地元企業との協力や地域住民からの定期寄付や寄贈を募る仕組みを整え、安定的な資金調達を目指します。さらに、企業の社会的責任(CSR)活動と連携し、具体的な支援を呼びかけます。現在、行政との協働も検討中であり、地域福祉事業としてカフェ・ドゥ・チルミルを活用できれば、さらなる支援の拡充や地域課題の共有が可能になります。社会的認知の不足は大きな課題です。地域住民や企業が、医療的ケア児者とその家族が直面する生活課題を理解し、支援する環境づくりが不可欠です。そのために、家族の声を伝える広報活動や、地元メディアと連携した情報発信を強化します。カフェ・ドゥ・チルミルは地域共生社会の実現に向けた第一歩です。今後はオンラインを活用した交流プログラムなどにより、仙台市以外にもこのモデルを展開し、全国的な支援ネットワークを構築する計画です。支援の輪を広げ、医療的ケア児者とその家族をより多面的に支援できる社会を目指します。
医療的ケアが必要な方々とそのご家族が、地域社会の中に自然に溶け込む風景。それが、社会福祉法人あいの実の目指すビジョンです。
まだまだ走り出したばかりの私たちの挑戦をどうぞご支援ください。