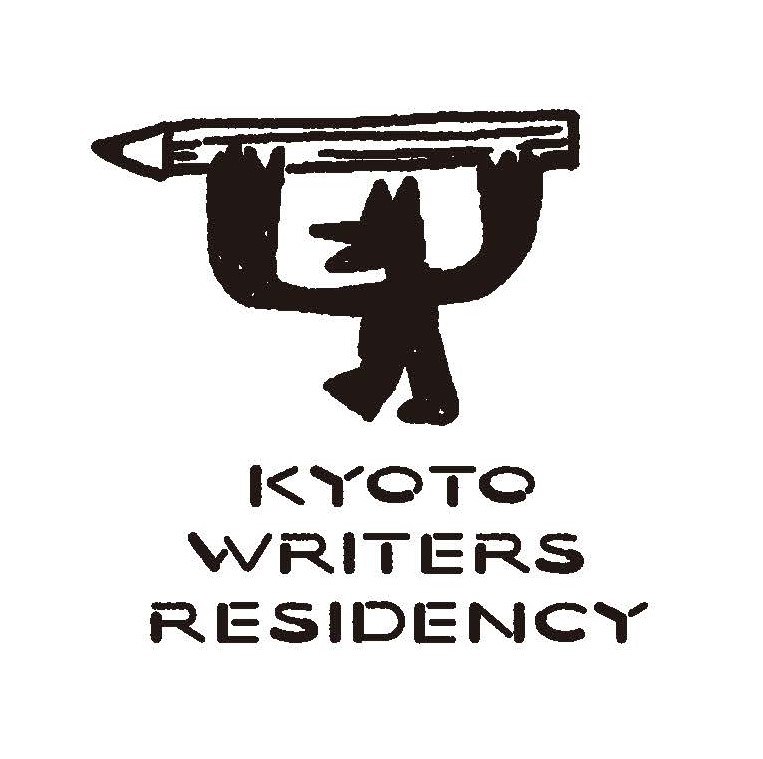文学レジデンシーとは
世界各国の作家や詩人、翻訳家を自国に招き、長期滞在というかたちを取りながら、創作の支援を行う活動です。日本ではまだ聞き慣れないですが、世界では70ヵ国、490もの施設が参加し、積極的に文学レジデンシーを開催しています。
その歴史は古く、1666年にフランス王立アカデミーがメディチ家の別荘を買い取り、芸術家をローマに滞在させたことが起源と言われています。その後、時代の中でアート・イン・レジデンス(AIR)事業は形を変え、現在では、芸術家が日頃とは異なる文化・環境に長期滞在し、現地の人々や他国のアーティストから刺激を受けながら創作活動を行うという意義が広く認知されています。海外では、文学者を含むアート・イン・レジデンスや文学専門の文学レジデンシーが展開されており、国を超えたコラボレーションや新しい価値の創出につながっています。
たとえば文学レジデンシーとして最も有名なアイオワ大学のIWPプログラムでは、3か月弱・30数か国の作家がアイオワに滞在し、創作やリサーチを行ってもらい、同時にシンポジウムや朗読会などの形で現地のコミュニティの対話・交流を図り、お互いに刺激を受け合います。
日本にも文学レジデンシーの文化を根付かせたい。私たち京都文学レジデンシー実行委員会は、そんな思いから、日本初となる国際的な文学レジデンシーの開催を目指して2021年に発足しました。
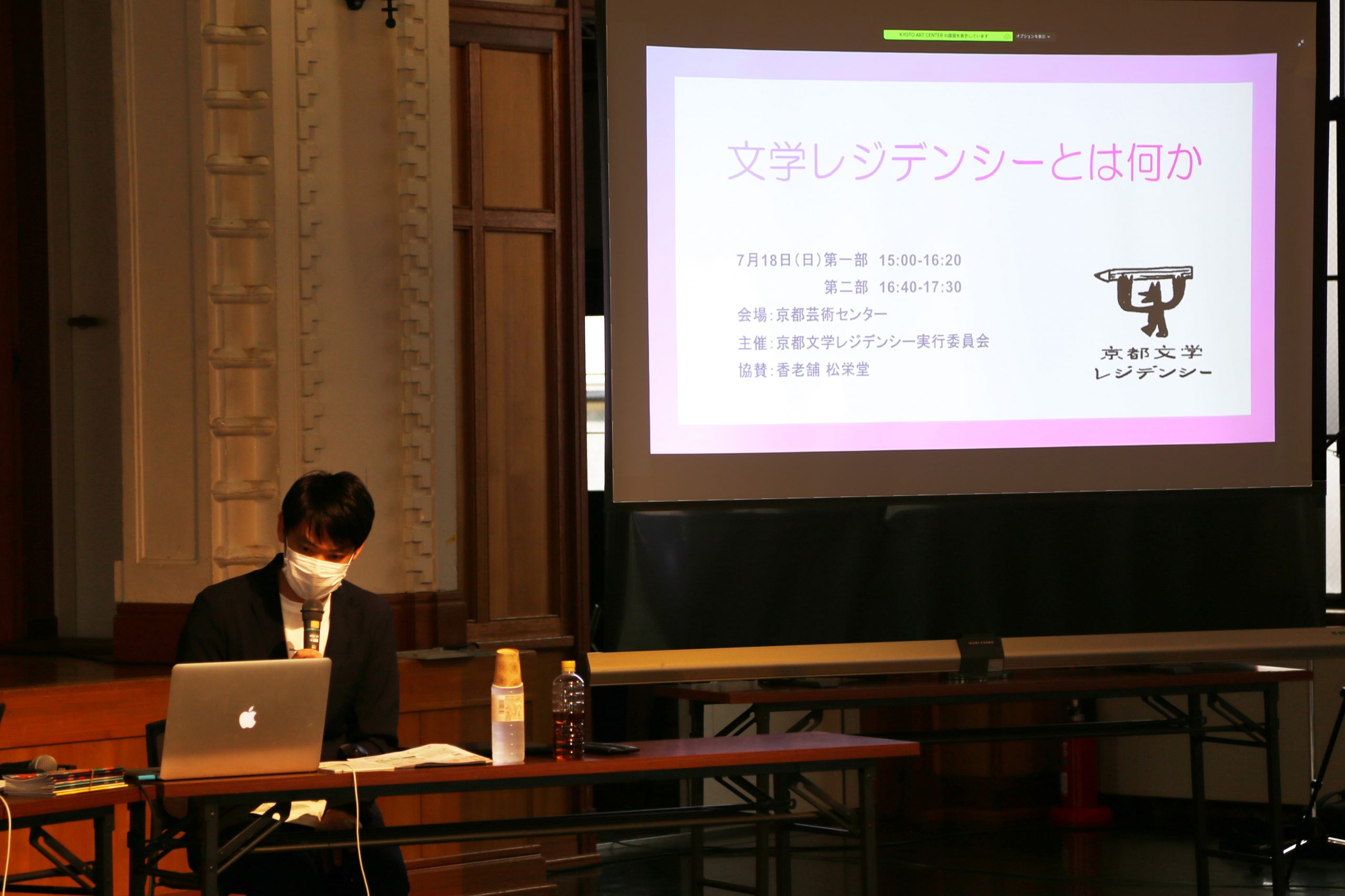

京都文学レジデンシー
京都文学レジデンシーでは、海外を拠点とする若手・中堅の作家を招へいし、ひと月ほど京都に滞在してもらいます。滞在期間中には、シンポジウムや朗読会などのイベントに登壇してもらい、世界文学の担い手たちが向き合う"いま"について、京都や国内の読者とも交流する機会を設けます。
日本の作家にもレジデンシーに参加してもらい、創作に専念する文学レジデンシーの意義を体験してもらうのはもちろんのこと、京都での国際的な交流を足掛かりに、海外のレジデンシーや文芸フェスティバルへの参加など、作家の海外進出の橋渡しとなる環境を提供したいと考えています。
また、日本(語)文学を諸外国語へ翻訳している翻訳者もあわせて招へいします。翻訳者に日本文化をより深く知ってもらい、日本の作家と直接話し合う機会を増やすことで、世界へ日本文学を発信する契機になればと期待しています。
開催実績
京都文学レジデンシーは、2022年に第1回を開催しました。応募人数や応募者の国籍やし執筆言語、およびパートナー団体・企業は、毎年増加し続けています。
2022年 京都文学レジデンシー01
招聘作家:6名(公募せず)
大前粟生(Ao Omae)日本
アンナ・ツィマ(Anna Cima)チェコ
アルフィアン・サアット(Alfian Saʼ at)シンガポール
エミリ・バリストレーリ(Emily Balistrieri)アメリカ
ポーラ・モリス(Paula Morris)ニュージーランド
ユベール・アントワンヌ(Hubert Antoine)ベルギー
パートナー団体および企業数:11
2023年 京都文学レジデンシー02
招聘作家:5名
佐藤文香(Ayaka Sato)日本
モード・ジョワレ(Maud Joiret)ベルギー
ジョセフィン・ロウ(Josephine Rowe)オーストラリア
ルス・ヴィトロ(Luz Vítolo)アルゼンチン
カン・バンファ(Kang Bang-hwa)韓国・日本
公募応募者数:59 名
公募応募者の国籍と執筆言語:30 カ国17 言語
アイルランド/アメリカ/アルゼンチン/イギリス/イスラエル/イタリア/インド/オーストラリア/オーストリア/オランダ/カナダ/ギリシャ/ケニア/スウェーデン/スコットランド/スペイン/タイ/台湾/チェコ/ドイツ/日本/ニュージーランド/ノルウェー/ハンガリー/バングラデシュ/フィリピン/フランス/マレーシア/南アフリカ/ルーマニア
パートナー団体および企業数:13

(2023年 クロージング・イベント開催風景)
2024年 京都文学レジデンシー03
招聘作家:10名
アンバー・アダムズ(Amber Adams)アメリカ
オーシュラ・カジリューナイテ(Aušra Kaziliūnaite) リトアニア
クレア・ウィグフォール(Clare Wigfall)イギリス/ド イツ
コリーン・マリア・レニハン(Colleen Maria Lenihan)ニュージーランド
ダリオ・ヴォルトリーニ(Dario Voltolini)イタリア
クリスティナ・ドンブロフスカ(Krystyna Dąbrowska)ポーランド
今宿未悠(Mew Imashuku)日本
パオロ・ティアウサス(Paolo Tiausas)フィリピン
ポリー・バートン(Polly Barton)イギリス
トリスタン・ルドゥ(Tristan Ledoux)ベルギー
公募応募者数:187 名
公募応募者の国籍と執筆言語:52 カ国36 言語
アイルランド/アメリカ/アルゼンチン/イギリス/イスラエル/イタリア/イラン/インド/インドネシア/ウズベキスタン/オーストラリア/オーストリア/オランダ/ガーナ/カザフスタン/カナダ/韓国/ギリシャ/クロアチア/ケニア/コロンビア/シンガポール/スウェーデン/スペイン/スロバキア/タイ/台湾/チェコ/中国/デンマーク/ドイツ/トルコ/ナイジェリア/日本/ネパール/ハンガリー/フィリピン/フィンランド/フランス/ブルガリア/ベトナム/ベネズエラ/ベリーズ/ペルー/ポーランド/マレーシア/メキシコ/モンゴル/リトアニア/ルーマニア/ルクセンブルク/ロシア
パートナー団体および企業数:21

(2024年 オープニング・フォーラム開催風景)
作者と読者が出逢える街・京都に
作家の"顔"が見え、"声"が聴ける体験は貴重です。京都文学レジデンシーでは、書店などでの朗読会やトークイベントを通じて、じかに世界文学の担い手たちの"声"が聴ける場を提供していきます。彼らの"声"に耳を傾けることは、私たちが日ごろ見過ごしている物事や捉えそこなっている問題に新たな目を向けるきっかけとなるでしょう。
京都には千年をこえる文学の歴史があります。『源氏物語』はアーサー・ウェイリーらの翻訳を通して、世界を魅了しました。異なる文化が出逢うことで、新たな"声"が生まれ、文化は豊かな広がりを見せてゆきます。
京都で、お互いの"顔"が見え、双方の"声"が響きあう環境が生まれることで、作者と読者の中に新たな文化が芽吹き、大きく花開いていくことを願っています。

京都文学レジデンシー実行委員会メンバー
京都文学レジデンシーは、京都にベースを置き、創作・翻訳に携わる各大学の大学教員を中心にボランティアベースで運営に携わっています。実行委員会常任委員メンバーは、下記の通りです。 ※2025年4月時点
- 吉田 恭子 (代表; 作家・翻訳家・京都大学)
- 澤西 祐典 (作家・龍谷大学)
- 藤井 光 (翻訳家・東京大学)
- 河田 学(文学理論・創作教育研究・京都芸術大学)
- 江南 亜美子 (書評家・京都芸術大学)
- 宮迫 憲彦 (CAVA BOOKS代表)
- 勝冶 真美 (滋賀県立芸術の森)
- 西岡 亜紀 (比較文学者・立命館大学)
- 小林 久美子(アメリカ文学研究者・京都大学)
- 谷口 弘信(京都市文化市民局文化芸術企画課文化力活用創生担当課長)

(実行委員会の中心メンバー。写真左から、河田、藤井、吉田、澤西、江南)
アドバイザリー・ボード一覧
運営に当たっては、下記アドバイザリー・ボードからアドバイス・協力をいただき、適切な運営に努めています。
- 藤野 可織 (作家・京都精華大学非常勤講師)
- 谷崎 由依 (作家・翻訳家・近畿大学准教授)
- 柴崎 友香 (作家)
- 辛島デイヴィッド (作家・翻訳家・早稲田大学准教授)
- ジョシュア・イップ (詩人・シング・リット・ステーション(シンガポール)代表)
- ケイト・グリフィン (英国作家センター・アソシエイト・プログラム・ディレクター)
- マーティン・コルソープ (Modern Culture(英国)代表)
ご支援の使い道
京都文学レジデンシーでは、寄付サイトを通じてみなさまからのご支援を募集しています。ご支援の二通りの方法がございます。
まず一つ目は、年単位で継続的にご支援いただく「サポーター制度」です。設定金額は下記の3種類からお選びいただけます。
- ちょこっとサポーター:3,000円/年
- しっかりサポーター:5,000円/年
- がっつりサポーター:10,000円/年
一年を通して継続的に応援いただけることは、実行委員にとって大きな励みとなります(途中での解約も可能です)。
もう一つの方法は、その都度ご支援をお寄せいただく「単発寄付」です。こちらは 2,000円から ご支援いただけます。
京都文学レジデンシーの試みは、皆さまからのご支持があって、初めて成功と呼べるものになります。文学レジデンシーの恩恵は作家や翻訳者といった創作者のみが受けるものではなく、読書コミュニティの充実や都市文化の発展といった形で、読者や一般の方にも広がっていくものです。また、文学レジデンシーの試みが京都に留まらず、日本各地へ広がっていくことを実行委員一同強く願っております。
私たちの活動は、皆様からのご支援によって成り立っております。皆さまからのご寄付は、文学レジデンシー事業で発生する運営費として大切に使用させて頂きます。百年続く、文学レジデンシーを目指して、一人でも多くの方から温かいご支援を頂けますよう、実行委員一同、心よりお願い申し上げます。