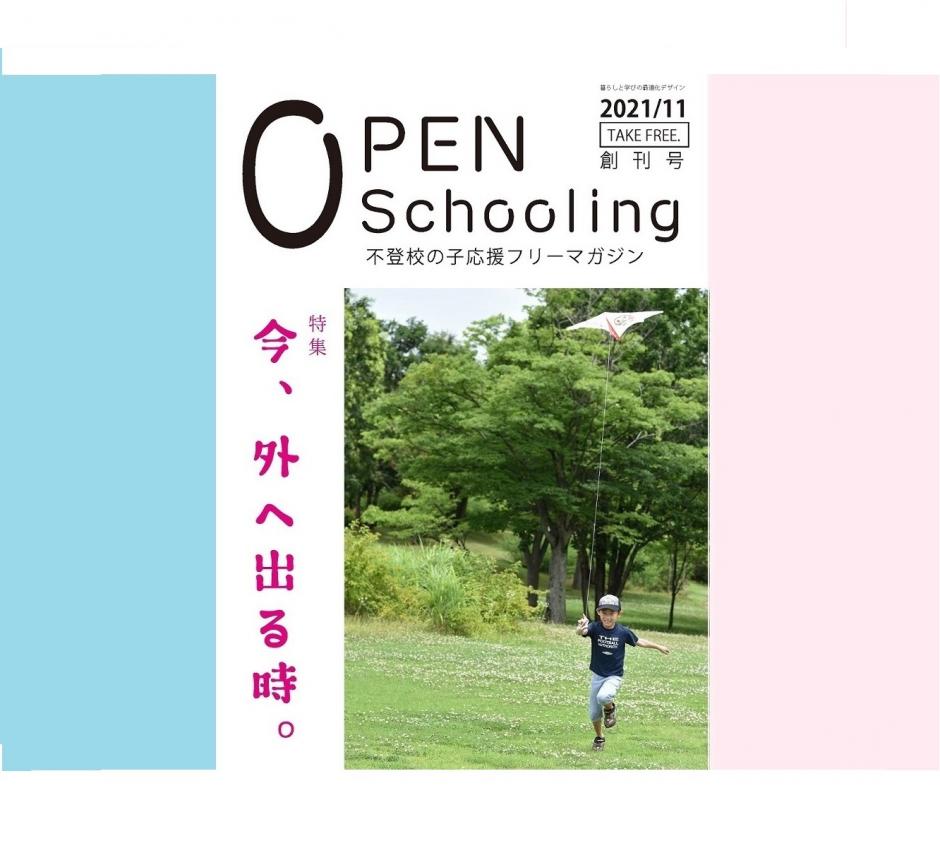なぜ不登校の子応援フリーマガジン?
私たちが、不登校についてのカウンセリングや心理支援をしていて感じていることは、不登校は本人だけの努力によって解決するものではないということです。
たとえ、不登校の子ども自身が、自尊心を得て、自分にとって最適な暮らし方や学び方を見つけることができたとしても、社会の側にそれを支える諸条件が揃っていなければ、その子は自己実現を果たすことができません。
そんな思いから、私たちは、不登校の子応援フリーマガジン『OPEN Schooling』を創刊しました。不登校の子も、その保護者も、その支援者も、その子の周りの方々も、同じ価値を共有し、その子の自己実現を支えてほしいと考えたからです。
おかげさまで、創刊号は新聞やブログ、SNSなどのメディアでたくさん取り上げていただき、増刷に増刷を重ねるほどの反響をいただくことができました。
今後は、本誌を季刊発行するとともに、より不登校の子の現在に根ざしたライフスタイル情報誌として成長させていきたいと考えています。
どんなフリーマガジンなの?
○フリーマガジンの体裁
・A5サイズ
・右綴じ
・20-30ページ
・フルカラー
・光沢紙
○フリーマガジンのコンテンツ
・毎号1-2名の当事者インタビュー
・毎号1-2名の支援者インタビュー
・毎号1-2名の教育関係者インタビュー
・掲載依頼に応じた記事
・特集(不登校のQOLを向上させるための情報)
▷特別な仕組み1:協賛施設・店舗とは
『OPEN SCHOOLING』を設置させていただく、施設・店舗は、ただの頒布協力先ではありません。このマガジンを設置しているお店や施設は、不登校お出かけサポート加盟店でもあります。学校のある日の日中に小中高生が来店した際に、安心して過ごせるようにすることに協賛する施設・店舗です。
このフリーマガジンには、このような形で日中に不登校の子どもたちが安心して外に出てオープンスクーリング(学校よりも広い場での学び)をすることができる仕組みがもう1つあります。
▷特別な仕組み2「オープンスクーリング・パスポート」ページとは
学校のある日の日中にお出かけをしていた時、どうしてこの時間にここにいるのかということを善意で聞いてくださる方がいらっしゃいます。そんな時に、「オープンスクーリング・パスポート」ページを提示することで、不登校の子どもが自分の言葉で事情を一から説明し、理解を得る必要がなくなります。このページには、「学びのための外出中」であることが説明されます。
これらのページを提示することができるようにすることで、不登校の子どもたちが、ホームスクーラーからオープンスクーラーへと学びの場を広げていけるようになることを期待しています。
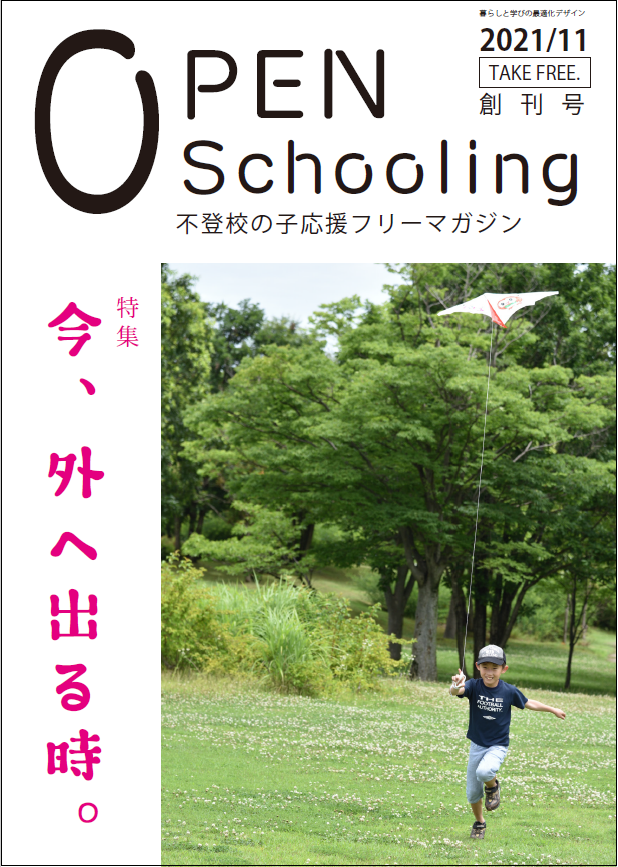
何を目指すの?
私たちが、このフリーマガジンの発刊で目指していることは、不登校というライフスタイルをもつ子どもたちが、自分の置かれた環境で、自分の暮らしと学びを最適化し、自己実現を果たすためのお手伝いをすることです。
すべての子どもが、安全・安心で、文化的な生活を営む権利をもっています。その権利は、学校に毎日行っていることが条件ではありません。無条件の権利としてもっているのです。
ですが、現在の社会では、学校に行っていないというたった一つのできないことが、様々なリスクを子どもたちに負わせる仕組みとなっています。
学校に行っている子も行っていない子も当たり前に、安心・安全で、文化的な生活を営むことができるようにすることは、私たち大人の課題です。
「学校に行ってもいないのに、日中出歩くなんて・・・」
「学校に行っているはずの時間は、学校と同じように・・・」
「あなたがやりたいことより、学校で学んでいるはずのことを・・・」
これらの意識は大人の側の意識であって、本人の課題ではありません。本人も、保護者も、支援者も含めた社会全体が意識改革を求められています。
私たちは、このフリーマガジンを発刊し、多くの方に読んでいただくことで、社会全体の意識改革を促していきたいのです。
↓令和4年4月発刊予定の第2号表紙
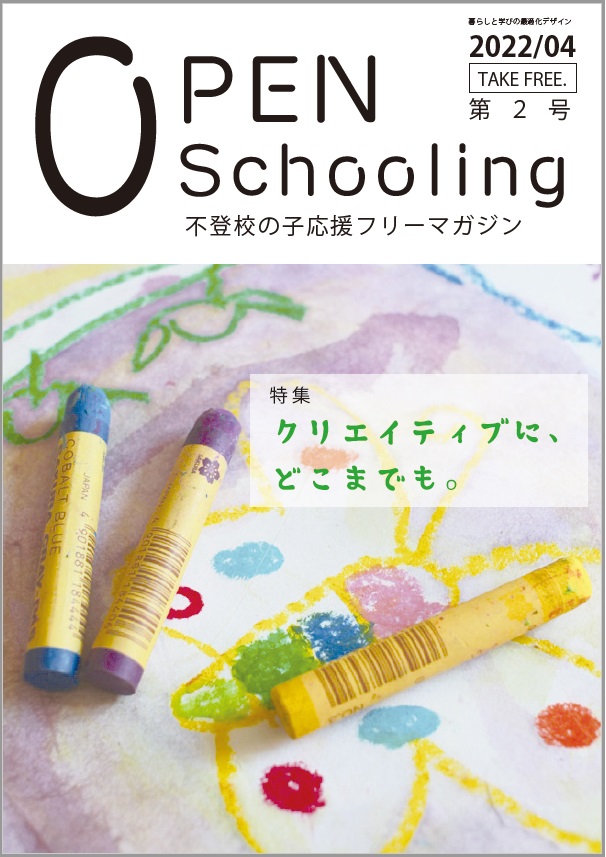
ご支援の使い道
このサイトからのご寄付につきましては、すべて不登校の子応援フリーマガジン『OPEN Schooling』の発刊費用として充てさせていただきます。
5000円のご寄付で、およそ100部のフリーマガジンの発刊が可能となります。
不登校に関係する多くの方に、不登校の暮らしと学びの最適化のアイデアが届きますようにご支援をお願い申し上げます。