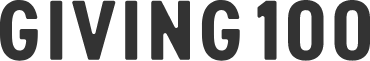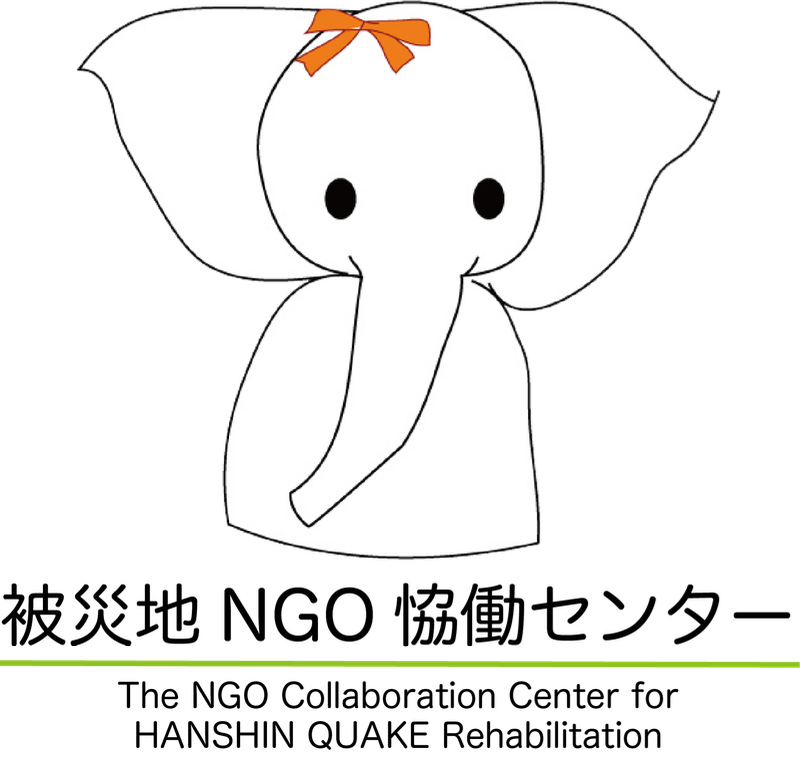第八次やさしや足湯隊は5/3~5/6の期間でボランティア活動をしました!
今回は学生6名にCODE海外災害援助市民センター事務局長吉椿雅道さんが同行しました。
本記事では、足湯隊の活動内容をご紹介します♪
5/3
被災地NGO恊働センターの拠点となっている七尾市中島町小牧に到着後、足湯講習会👣
足湯ボランティアや災害ボランティアに初めて参加される方も多くいらっしゃるため、足湯隊ではまず初日に足湯講習をしています。

5/4
午前中は、珠洲市蛸島町の「北前船 三蔵(さんぞう)の家 旧島崎家」の保存活動をされているAさんと一緒に瓦の片づけ活動です。

北前船とは、江戸時代、北海道・東北・北陸と西日本を結んだ西廻り航路は経済の大動脈であり、この航路を利用した商船のことです。瓦の片づけを行った島崎家は珠洲から北海道江差町などへ商品や人を運んだ北前船二隻を所有していた家屋でした。
被災前は、「奥能登国際芸術祭」なども開かれていた旧島崎家。Aさんのお話を聴きながら、一枚一枚の瓦を学生達で丁寧に外し、整理していきました。
午後は、輪島市鳳来保育園にて足湯ボランティア活動でした。
学生たち一人一人で被災された方の「つぶやき」に向き合います。

また、輪島市の朝市通りも訪れました。「やさしや足湯隊」では学生や若者が被災地の様々な現状を受け止めることで、参加者がそれぞれが考え、行動に移すきっかけとなっています。

学生ボランティア 感想(一部抜粋、全文は後日配信予定)
自分が特に印象に残っている場面は二つあります。一つ目は、輪島市にある朝市を視察した事でした。 現地の独特な雰囲気、火災現場後の煤の匂いや一面焼け野原になった街は忘れる事は無いと思います。自分は街を歩いている時に、火災で燃えている家を背に避難する姿、津波警報が出て逃げまとう姿や瓦礫の中から救出しようとする姿を想像しながら歩いていました。 その様に出来たのは現地に行けたからだと思います。・・・(玉地紘樹 神戸学院大学二年)
5/5

午前中の活動は、前日と同様に「北前船 三蔵(さんぞう)の家 旧島崎家」にて瓦の片付け作業。
北前船の木の図面が出てきたため、Aさんも「お宝が出てきた!」「北前船を作る夢ができた」と大変喜ばれていました。
学生ボランティア 感想(一部抜粋、全文は後日配信予定)
島崎邸の瓦の片付けのお手伝いでは、以前は表側だけが終わった状態だったが、今回は人数も多く、あと一回ほどで全て終わりそうなくらいまで片付けが進んだ。その中で北前船の木の図面が新たに見つかった。おそらく屋根裏にあったため誰の目にも触れることがなかったものであり、Aさんもとても喜んでいた。公費解体の前にこうして大切なものをしっかりと助け出すことができて本当に良かったし、多くの人が大切なものを取り出せればと思った。(今井愛梨 聖路加国際大学一年)
午後は二班に分かれて、穴水町前音楽教室と珠洲市三崎小学校横 仮設住宅の談話室にて足湯ボランティア活動でした!
穴水町前音楽教室では、6名いらっしゃいました。場所を貸していただいた前さんは普段音楽教室や音楽健康体操などをされています。
足湯には近隣の方々や、ボランティア活動で炊き出しをされていた方も来られました。

珠洲市の仮設住宅の談話室にて行った足湯ボランティアにも多くの方が来られました。

学生ボランティア感想(一部抜粋、全文は後日配信予定)
足湯をしている中で皆さんに共通していたことが、「普段から仲がいいから、それが一番の支えになったり頑張れたりしている」という言葉。しんどい思いや大変な思いも言っていたけど、周りの人との繋がりがあるから前向きに頑張っていると感じた。(石塚碧士 神戸学院大学二年)
足湯隊としての活動は、個人的には大成功だった。もちろん反省点は色々とあるが、良かった点を振り返る。・・・ 5日の三崎小学校での足湯ボランティアは、談話室の重要性を感じられた。仮設住宅に避難する高齢者は一人で生活している方も多いため、孤立してしまうことが多い。しかし、談話室で足湯をするとなると近所の人を呼びに行き、「私も行くから一緒に足湯行こ」という会話が生まれ、家に一人でいた方も外に出ることができた。孤立した仮設住宅の中にコミュニティを形成できる談話室という存在は非常に重要な役割があると感じた。実際に集まった住人同士の会話は尽きないほどの盛り上がりだった。(岩尾正貴 神戸学院大学二年)
5/6
活動最終日は、被災地NGO恊働センターさんの活動のお手伝い。災害ゴミの搬出や、家屋の片付けを手伝いました。


参加学生 感想(一部抜粋、全文は後日配信予定)
私は今回が1回目の足湯隊の参加で、発災からおよそ4ヶ月の被災地に足を踏み入れること、足湯をすることなど初めてのことを多く経験した。今回に限らず、被災地にボランティアとして足を運ぶことは私にとってはとても緊張するし、いく前は自分が行って何ができるのだろうか、と不安を感じていた。実際に行ってみて、ボランティアにできることはたくさんあるし、必要とされている場も多くあるのだろうと感じた。一方で、現場とボランティアがうまくつながっていないという状況や何かしたいけれどその気持ちがうまく活動に結びついていないのではないか、ということも現地の方や他のボランティアとの交流から感じ取れた。足湯は特別な技術がいるわけではなく、話のきっかけにもなるし、対話のツールの1つとして、そして被災地の方にリラックスしてもらうのにとてもいいと思う。だからこそ、足湯隊はより広がる可能性を持つのだと思うが、どんな人に、どれだけの人に今後足湯隊を広げていくのかも気になった。(山本結子 神戸大学二年)
私は今回、初めて能登半島地震の被災地を訪れました。そして、復旧のさなかにある被災地を訪れたのも初めてでした。この3泊4日を一言で表すのは難しいですが、自分には何もできないのだと無力感を覚えるときもあれば、自分でも役に立てることもあるのかもしれないという少しの自信を持てるときもありました。・・・そのような中でも、私なりに考えながら、被災された方に寄り添いながら足湯をさせていただいたとき、被災された方がご自身の若いころのお話を語りだされたり、終わった後に明るい表情を見せてくださったりしたことは、とても心に残っています。正直なところ、当初はボランティア経験の乏しい私にできることがあるのかと不安に思いながら参加しましたが、私にもできることがあるのかもしれないと思えた時間でした。(中沢優希 大阪大学四年)