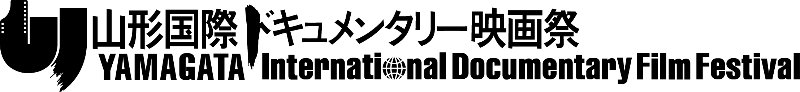ドキュメンタリー映画祭で、何よりも気持ちがたかぶるのは、作家たちとの遭遇の瞬間だろう。遭遇というのは、あらかじめ出会いを期待し、遠目に見つつ内心賞賛を告げるのとは異なり、上映会場の内外で思いがけず生身の(!)作家とすれ違い、時には大胆にも声を交わし、運が良ければ一緒に酒を飲んだりできるところだ。
審査員として来ていたロバート・クレイマーから、たまたま映写の中断で出てきたロビーで、上映中だったフレデリック・ワイズマン『コメディー・フランセーズ』についての評を聞くことができたり、別の時には、大ホールのロビーで、リティ・パンから、いずれは彼自身の家族の物語を語る作品を撮りたいのだが、しかし、自分の家族のこととなるとなかなか踏み出せないのだ、という意味のことを聞いたりした。あの時のリティの自らの内部覗き込むような目つき、静かなもの言いは忘れ難い。

※画像は、2019年に発売したYIDFF30周年記念ポストカードセットの1枚、1997年に来場したロバート・クレイマー氏とフレデリック・ワイズマン氏。
作家の声に触れること、それは、まさに映画祭ならではの経験で、その前提には映画祭の場における作家の存在がある。物質的な存在という以上にまさに作品そのものを生きるかのようにその場にある作家の存在である。
しかし、それらの言葉は私の記憶の中にしかない。記録を残せばよかったのか、それもまた映画祭における幸運の一つとして自分だけの宝としておけば良いのか。
時には、作品について語ることを拒絶する作家だっている。作家は作品によって語れば良いのであって、それ以上を語るべきではない、と。
だからこそ、逆説的にも、インタビューは、まさに作家たちとの遭遇を、記憶されるべき出会いとして刻み込み、記録し、共有する稀有の場となる。作家の声を伝え、作家との出会いを残す継続的な「声」の場となる。

※写真は、YIDFF2025でモーレン・ファゼンデイロ監督(インターナショナル・コンペティション作品「季節」)にインタビューする阿部氏
たとえば、私が関わったもので言えば、『包囲:デモクラシーとネオリベラリズムの罠』の作家リシャール・ブルイエット(監督)とエリック・モラン(音楽)のインタビュー。想像以上に真剣そのものだった二人とのやり取りは、時に反論し議論するような部分もあっての充実した対話となった。作品製作の経緯から、実際の作品構成、編集の機微に至るまで、二人は実に誠実に語った。その時間は、私にとっても貴重な経験であったし、作家たちにとっても充実した時間だったらしく、モントリオールで再会した時には、本当に喜んで山形での日々を語ってれた。
最近で言えば、2023年の映画祭、『交差する声』の監督ラファエル・グリゼーへのインタビューも忘れ難い。それはグリゼーとブーバ・トゥーレの共同作業とも言うべき作品の成立についての心躍るような対話となったし、ことにラストの歌の美しさを熱く語る時間は素晴らしかった。そういう時間に出会えることこそ、インタビューの醍醐味である。
2025年の映画祭のラインナップからも、多くの熱い時間が生み出されるはずだ。
それはやっぱりきちんとした冊子の形で残したいな。
阿部 宏慈

※文中に登場するロバート・クレイマー氏が来場した際に収録したフレデリック・ワイズマン氏との対談の記事はこちらでお読みいただけます。
Documentary Box #12 対談:ロバート・クレイマー フレデリック・ワイズマン

金額3,000円 |

金額5,000円 |

金額5,000円 |

金額10,000円 |

金額20,000円 | 在庫18 |

金額35,000円 | 在庫26 |

金額3,000円 |

金額5,000円 |

金額5,000円 |

金額10,000円 |

金額20,000円 | 在庫18 |

金額35,000円 | 在庫26 |