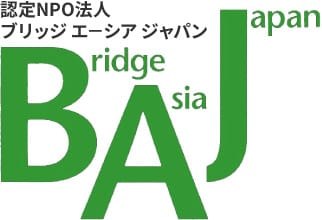拝啓 いつもミャンマーを気にかけてくださっている皆さま
いつもご支援を誠にありがとうございます。事務局長の新石です。
とつぜんですが、表題の件です。
中央乾燥地域の某村では、電線が来ているのに(いわゆるグリッドの電気があるのに)深井戸の水中ポンプを稼働させるためにはソーラー発電システムが必要だといわれました。なぜでしょう?
せっかく電線の電気があるんだから、それを使えばいいのに!!
答えの分かる方は、技術の知識がある方、もしくはアジアやアフリカなどの開発事情に詳しい方ではないかと思います。
恥ずかしながら私はわかりませんでした!
でも教えてもらって「そんなこともあるだろうなぁ」といたく納得したので、ご紹介します。そして、なぜ私が分からなかったのかについても発見があったので、合わせてお話しします。
*
先日、中央乾燥地域の次年度活動計画を立てるために、現地チームが30か村近くを訪問調査しました。
そこで、それぞれの村の井戸の修繕に、いま何が必要なのかを検討しました。
各村落の基本情報を見ながら、現地チームが作成した活動計画案に目を通していきます。すると、電気が来ている村なのにソーラー発電システムの設置が推薦されている村がありました。いったいなせなのか?
答えです。
現地スタッフに話を聞き、これは「電気のラストワンマイル問題」なんだとわかりました。電化やインフラ整備の分野で、Last-mile electrification または Last-mile connectivity として知られる問題の一つです。
つまり、送電線はあるけれど、発電所からの距離と容量不足で「力のよわい電気」しか村に届かない。変圧器やコンバーター、スタビライザーなどを付けても、根本的な解決にならない。けっきょく届いているパワーが少ないから、水中ポンプが満足に動かせない。揚水量が上がらない。――ということでした。
だから、この村ではダイナモとエンジンを使って電気をつくり、それで深井戸を稼働させます。ですが、昨今の物価高をはじめとした経済状況の悪化で、エンジンを動かす燃料代が高騰して、村の経済を圧迫しています。
そのため、燃料のコストが抑えられる太陽光発電システムが必要なのでした。
グリッドだけでは不足する電気を、補助的・代替的な発電システムを導入することで解決する。―― ざっと調べてみると、こうした問題と対応策は世界的によくあるケースでした。
じゃあなぜ「あるある」なのに私は分からなかったのか?
いろいろ調べて気づいたのは、おのれが世間知らずであることはもちろんですが、日本が世界的に見て特異なほどに電気の安定供給が実現している国だからでした。(日本スゴイ! 有り難い!でも知らないことの怖さ!)
だから無邪気に「電線の電気をつかえばいいじゃない?」と現地スタッフに投げかけてしまいました。災害が起こったときの計画停電の経験はありますが、ラストワンマイル電化問題は想像できていませんでした。
恥をしのんでご報告します。「へぇ~!」でも「そんなことも知らなかったのか!」でも、何かしらの知的な刺激、そしてミャンマーの村落部やインフラ状況の理解につながりましたら幸甚です。精進します。
いつも応援していただき感謝申し上げます。