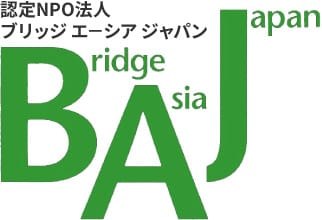拝啓 ミャンマーの被災地を気にかけていただいている皆さま
いつもご支援をありがとうございます。事務局長の新石です。個人会員 Nisidaさんが書いてくださった被災地レポート後編をお届けします。紀行文としても絶品です。ぜひご一読ください。
いよいよクラファンも残り7日。夏もおわりを感じて名残惜しい! さいごまで走り抜けます!!
*
ミャンマー被災地レポート(2025年6月29日) NISHIDA Koichi
ネピドーから車で30分ほどのところにあるピンマナという町の被災状況を視察した。首都ネピドーが建設されるまではこの地域の中心都市だった。この町では147人が亡くなっている。車の中からだけの視察となった。

倒壊した家屋はおおむね撤去されているようだが、地震直後は大変な状況だったと思う。それでもまだ、あちこちで瓦礫を撤去している人々が見られる。主にレンガ造の家屋が崩壊している。その反面、薄く割いた竹を格子に組んだ壁とバナナの葉の屋根で作られた伝統家屋は壊れていない。軽いからだろう。

レンガの瓦礫はさらに小割りされて、町はずれの道路脇の低地に敷き詰められていた。時間がたてばぬかるんだ低地は水はけのよい宅地に代わるのだろう。合理的なリサイクルである。赤土のテニスコートをアンツーカーといって、砕いたレンガを材料にしていることを思い出した。レンガは昔からこのようなリサイクル手法が定着しているのかもしれない。

(上写真:敷きつめられたレンガがれき)
翌日、ネピドーから車で2時間ほど北上したピョウボエという町を目指す。ハイウェイを外れて旧の国道1号を走る。かろうじて車が離合できるぎりぎり2車線の舗装道路を延々と走る。車道の外にはもう1車線分の未舗装帯があるが、ここは主に牛車が通る。牛車(ぎっしゃ)といえばかぐや姫に出てくるような平安貴族が乗るアレを想像するが、ここではブルカートと呼ばれる4頭立ての埃まみれの荷車だ。前に2頭、後ろに2頭。後ろの2頭はつながれているだけなので交代要員なのだろう。正確には2頭立てである。これが何台も何台もやってくる。白いウシばかりだ。この国ではウシは貴重な輸送手段であり労働力でもある。

(上写真:国道1号を行き交うブルカート)
ピョウボエは震源地となったマンダレー管区域に属する。街の中心部で村落開局職員が待っていてくれて同行する。昨日会った村落開発局本部の部長の配慮だ。

(上写真:ピョウボエ中心部の踏切。待ち時間が長い)

最初に訪れたのはキリスト教の教会。数人の作業員が長机を作っている。これは被災した学校へ贈る教室机とのこと。木製机が全壊したので、軽量鋼製フレームに板を張った机を制作している。この費用にはBAJが募っているミャンマー被災地支援募金も含まれている。
次に校舎が倒壊した学校へ向かった。その道中でも多くの被災した家屋を目にする。ここでも倒壊家屋のほとんどはレンガ造だ。この町の土は赤っぽいシルト交じり砂である。砂地盤なのに液状化の跡は見られなかった。地下水位はそれほど低くはないと思う。適度なシルト分が液状化を食い止めたのかもしれない。真新しい白い避難テントには赤十字のマーク。市場でも瓦礫撤去や復旧作業で多くの人々が作業していて、土ぼこりが街全体に漂っている。その中でも倒壊しなかった建物には沢山商品が並べられ、多くの買物客が行き来する。十字路を通るたび、左右の通りの見渡す限り先までずっと、この光景、つまり倒壊家屋と土ぼこりと商店と多くの買い物客が続く。人々の生きるエネルギーが伝わってきて圧倒される。



車一台がやっと通れる泥道を進んだ先にその小学校はあった。4つほどの教室がある木造平屋建ての校舎。被災していない3つの教室では子供たちが授業を受けていた。案内してくれた教員は校庭を指さして、ここに校舎に向かって地割れができたのだという。砂地に草が生えているので、3か月目の断層面はよくわからなくなっている。

倒壊した教室は屋根が落ちていて、南北面の壁が倒れている。横に回って見てみると、地割れに沿って2m程横ずれしていた。地震エネルギーの凄まじさを感じる。断層面の西側は北へ、東側は北へずれたとする国土地理院の報告とも合致する。

(上写真:手前の2本の柱は奥の柱と一直線だった)

(上写真:校舎北側からの破損状況)
校舎の復旧スケジュールはまだ決まっていない。もともとは地域の親たちが資金を出し合って建てられた学校だという。草っ原の校庭に仮設の校舎の建設が進められていた。作業しているのは、先の教会の神父が音頭を取っているボランティア団体だそうだ。
5日間、駆け足で被災地を回ってきたが、被災地の辺縁部を垣間見たに過ぎない。発災後、3か月が経過するが、深刻な事態が継続している地域がまだまだ存在するのだと思われる。
フェーズとしては、復興局面にはまだ遠く、復旧局面がまだまだ続く状況だ。生活手段やインフラの復旧のための、資材も重機も資金もまだまだ行きわたっていない。
遠く離れてはいるものの、かつて同じように被災の辛苦を経験した私たちに、いま何ができるだろうか。とかくクローズドにされがちなこの国の情報、まずは情報を少しでも発信し、広めていくことから始めていこうと思う。 <了>