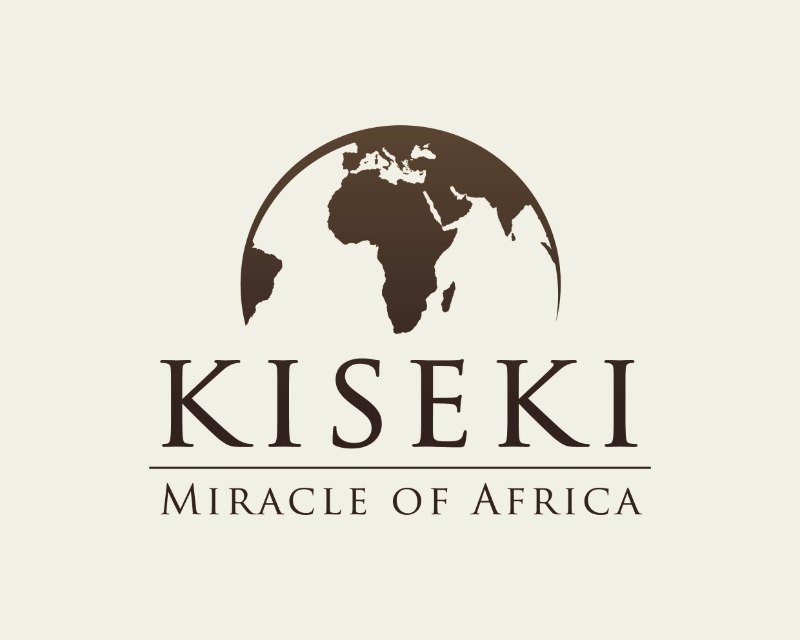高級レストランからソーシャルビジネスへの大転換はあるママの勘違いがきっかけ!
みなさんこんにちは。キセキの女将山田美緒です。キセキが今の姿になるまでの約9年の歴史を紹介させてください(ご存じの方は読み飛ばしてください)
2016年に日本食レストランとしてキセキをスタートさせました。
度重なる従業員の盗みや不正に疲れ果て、シングルマザーで掃除係のMに「あなたみたいな真面目なママたちと働けたらなぁ」と愚痴をこぼしたところ…翌日50名を超えるシングルマザーたちが押し寄せました。「なんでもするから仕事をください」という彼女たち。職なし、学歴なし、経験なし、英語できない、お金なし、子持ち…こんな人たち誰が雇うというんだろう。よし!じゃあ私が雇おう!(論理の飛躍!?私自身も3人の子どもを育てる母として何かできるかも!何かしなくちゃ!放っておけなかったのです)
8名程度をレストランで雇用し始めました。しかし!レストランで働いたことがないどころかレストランに行ったこともない彼女たち。レストラン業務壊滅的!バナナを買いにでかけてパイナップルのほうが安かった!と買ってくる、ランチ営業始まっているのにゆっくり賄いを食べる、包丁でネジを回す、缶詰開ける、畑を耕す、木を切る(ヤメテクレ)…でもいいところもたくさんあったんです。お客さんの誕生日を一緒になって祝ったり、お客さんの子どもを一生懸命あやしたり、失敗しても辛いことがあっても仲間と助け合い笑って立ち上がる。
こんなママたちと過ごす日常を、経験を価値があると思ってくれる人は誰だろう?
という発想から始まったのがボランティア・インターンプログラムです。国際協力や国際交流、多文化理解や共生に興味のある方ならお金を払ってでもこの経験をしたいに違いない。初年度から100名ほどの方が参加してくれ大成功!ニーズがある!調子に乗ってママたちの子どもが通う幼稚園がないからと物置になって放置されていた建物を幼稚園として復活させレストランをしながら運営しました。
当たり前や常識、積み重ねてきたものがことごとく破壊される試練の連続、それでもやり続ける!
順風満帆に見えるキセキの活動なのですが、これまで3度の心ズタズタ事件と、1度の経済的大ピンチがありました。心ズタズタ事件のほうは本人の名誉のためにもここでは割愛します(「二度と私の人生に交わらないで」と絶縁したのに本人はしれっと幼稚園に娘を預け、道でばったり会って世間話をしてくる世界最強心臓の持ち主です)。経済的大ピンチはコロナで収入の9.9割を失ったこと(いや、レストラン0.1割って。もっと頑張れよ)
コロナ禍初期、「ZOOMって何?」の頃、エストニアの起業家Y氏の発案で2日で立ち上げたルワンダのママがオンラインで子どもと遊ぶ「オンラインベビーシッター」が成功し、さらにボランティア・インターンプログラムの卒業生や山田の友人や長年の支援者のみなさん、たくさんの方に現金での応援をいただいたおかげで乗り越えることができました。
コロナが終わってたくさんのお客様が帰って来てくれました。予約が1件、また1件と入り始めた時にはママたちと歌って踊って喜びました。
シングルマザーの雇用、幼稚園の再建から始まったKISEKIは2020年には託児所、子ども食堂、妊産婦ケアセンターを始動。2023年には縫製の訓練校を設立し、縫製サービスやアパレル事業もスタートさせ着実に事業を拡大してきました。
ボランティア・インターンプログラムを主な資金源として地域の最貧困家庭の母子に食事、教育、愛を中心に様々な支援を行っています。8人だったママは40名に。150名の子どもたちで溢れ、毎年150名を超える日本人が訪れています。
当初は「あの外人の目的はなんだ?」「貧しい人を使って金儲けしている」と言われていましたが、今は地域のパートナーとして一緒に地域の母子を取り巻く課題の解決に取り組んでいます。
しかし!!!コロナの後も予期せぬ病や国際情勢の変化により経済危機がたびたび訪れました。エムポックス、マールブルグ、コンゴでの謎の病気、そして今回のコンゴとの関係の悪化。「なぜ繫忙期ばかりに?」今日は何件のキャンセルの連絡があるだろう、ありませんように…祈る日々が続き、予約表と予算と帳簿を見つめる日々…ルワンダでの事業に「安定」はありません。
「寄付をお願いしてはいけない」勘違いをしていました
冒頭でも書いていますが、私たちは「かわいそうだから支援する」のではなく、「価値ある体験を提供する」ことで支援を拡大してきました。そして、日本人を受け入れている女性たちにも「あなたたちはかわいそうなのではない。誇りを持っていいのだ」と伝え、共に成長してきました。
レストランを閉店してから4年で数々の分野に手を広げ、攻めの支援をできたのもビジネスとしての強気の姿勢があったからだと思います。施しではなく価値を生み出す存在でありたい。
だから私たちは寄付をお願いしてはいけない。
そう想い込んできました。寄付をお願いすることは「弱さを見せること」、「頼ること」だと。でもこの考えのままでは続かないということに気づきました。
寄付をお願いすることで広がるのは、単なる支援の関係ではなく、「共に生きる」世界です。
私たちの活動には価値があると信じているからこそ、そして私たちならば変化を起こせると信じているからこそ、寄付をお願いしたい。
寄付は「ただ助けてほしい」ではなく、「一緒に未来をつくろう」と呼びかけることなのかもしれないと思い改めました。
活動を続ける中でキセキのお母さんたちが「支えられる人」ではなく、「支える人」として少しずつ成長していく姿を見てきました。私たちが支援した子どもたちは「与えられる人」ではなく「未来を創る人」になってくれるでしょう。
そして、その過程を支えてくださる日本の皆さんは「助ける人」ではなく「仲間」なのです。
寄付を通じて生まれるのは、単純なお金のやりとりではないということ。
それは、「頑張ってるから応援するよ!」という声が、ルワンダの女性たちの誇りになること。
それは、「こんなに遠くの誰かが、私たちの挑戦を見守ってくれているんだ」と、私たちの支えになること。
それは、「自分が送ったお金が、誰かの人生を変える実感」を寄付してくれた方に与えられるかもしれないこと。
キセキが創るのは、「かわいそうな人を助けるための社会」ではなく、「一人ひとりの力が集まり、小さな一歩の積み重ねが確実に世界を変えていく社会」
一人一人が手の届く世界に小さな違いを作ることができること。
小さな一つ一つの積み重ねが世界を確実に変えること。
そんな世界に共感し、一緒に広げてくれる人と繋がることができたら、こんなに心強いことはありません。
代表者メッセージ
さくっとまとめるつもりがついつい長くなってしまいました。
世界には日本にだって、たくさんの困りごとがあります。私たちの力ではどうしようもないことだってある。私たち一人一人にできることは限られている。こんなどうしようもない世の中だからこそ”今”自分の手が届く世界でできる最大限のことをやる。全力で、本気で精いっぱいやる。
変わるまで変えれば必ず変わる、小さなことを一つずつ着実に積み重ねてきましたし、これからも重ね続けていきます。
ここまで読んでくださって、私たち活動へ興味を持っていただき、支援を考えていただき本当にありがとうございます。

寄付金の使い道について
1円も漏らさず地域のお母さんが笑顔で暮らせる社会を創るために使わせていただきます。
朝150名の子どもたちに配るチャパティとイギコマ(お粥)(月12万円)
200名のママたち&子どもたちのランチの食材購入費(月40万円)
キッチンのガス代、水道代(月3万円)
80名の幼稚園児・小学生・中学生の学費(年間合計80万円※)
25名の託児所の赤ちゃんたちのおむつ(月2万円)
26名のスタッフに毎月配布する10㎏の米と5㎏の豆
幼稚園でICT教育をするためのインターネット(年間3万円)
※学費は1学期100円程度の学校もあれば、1万円近くする中学校もあり個人差があります。キセキは全スタッフの全子どもと、幼稚園120人中50名の学費を全額無償で支援しています。
他にかかる経費は過去のボランティアの方の作った仕組みや、寄付によって支えられています。例)
・妊産婦ワークショップ運営費 大阪のママグループがフリマの売上を寄付
・活動支援費 Mさんが寄付
・生理用ナプキン50名への無償配布 インターンSさんが立ち上げた各種ツアーの売上から捻出
・健康保険200名分を寄付 ボランティアHさんがキセキのテイラーが作った人形の売上を寄付
・5名の幼稚園児の支援 ボランティアの小学生Rさんが自身で描いた絵を売って寄付)
・4名の虐待児への土日の食事提供 ボランティアの中学生Kさんが講演会で募金を呼びかけ寄付
・農村部に離れて暮らすジャスティンの帰省費用 Mさんが寄付
などなど。