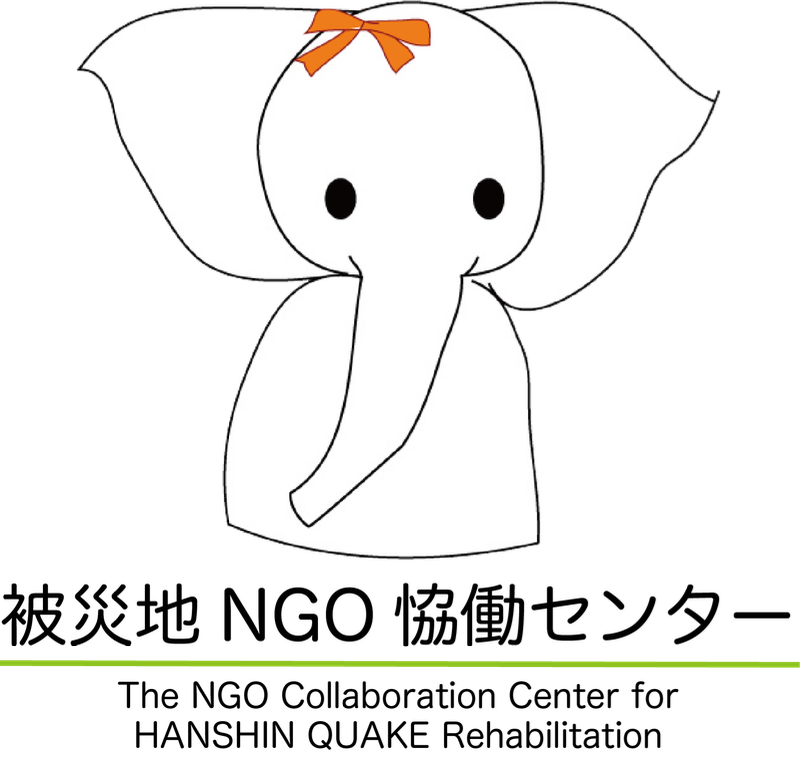2025年8月豪雨災害の支援活動を開始します!
2025年8月豪雨災害の支援活動を開始します。
8月9日からの大雨によって、各地に大きな被害が出ています。洪水で亡くなった方など、人的な被害も出ており、心からお悔やみを申し上げるとともに、甚大な被害を受けた方々にもお見舞い申し上げます。九州地方や石川県でも被害が拡大しています。
当センターが拠点を置く、石川県七尾市中島町でも未明の大雨により国道が大きく陥没し被害を受けました。連日の大雨により、地盤も緩くなっておりまだ油断ができない状況が続いています。
広い範囲で被害が出ており、被害の全容がまだ見えてきていないため、当センターでは、CODE海外災害援助市民センターと連携し、明日13日から情報収集のためスタッフを九州へ派遣いたします。また、今後の支援活動は佐賀県に拠点を置く「一般社団法人おもやい」とも連携をとりながら実施してまいります。
2024年能登半島地震、能登半島豪雨災害の支援も継続中です
2024年能登半島地震や能登半島豪雨災害の支援活動も継続しています。息の長い復興支援にもぜひご協力をお願いします。

代表の頼政です。
2007年から災害ボランティアを開始して、これまで25ヶ所以上の被災地でボランティア活動をおこなってきました。これまでの支援のノウハウを活かしながら、地域の皆さんと協力して支援を続けて参りたいと思っております。ぜひご支援・ご協力をお願いします!
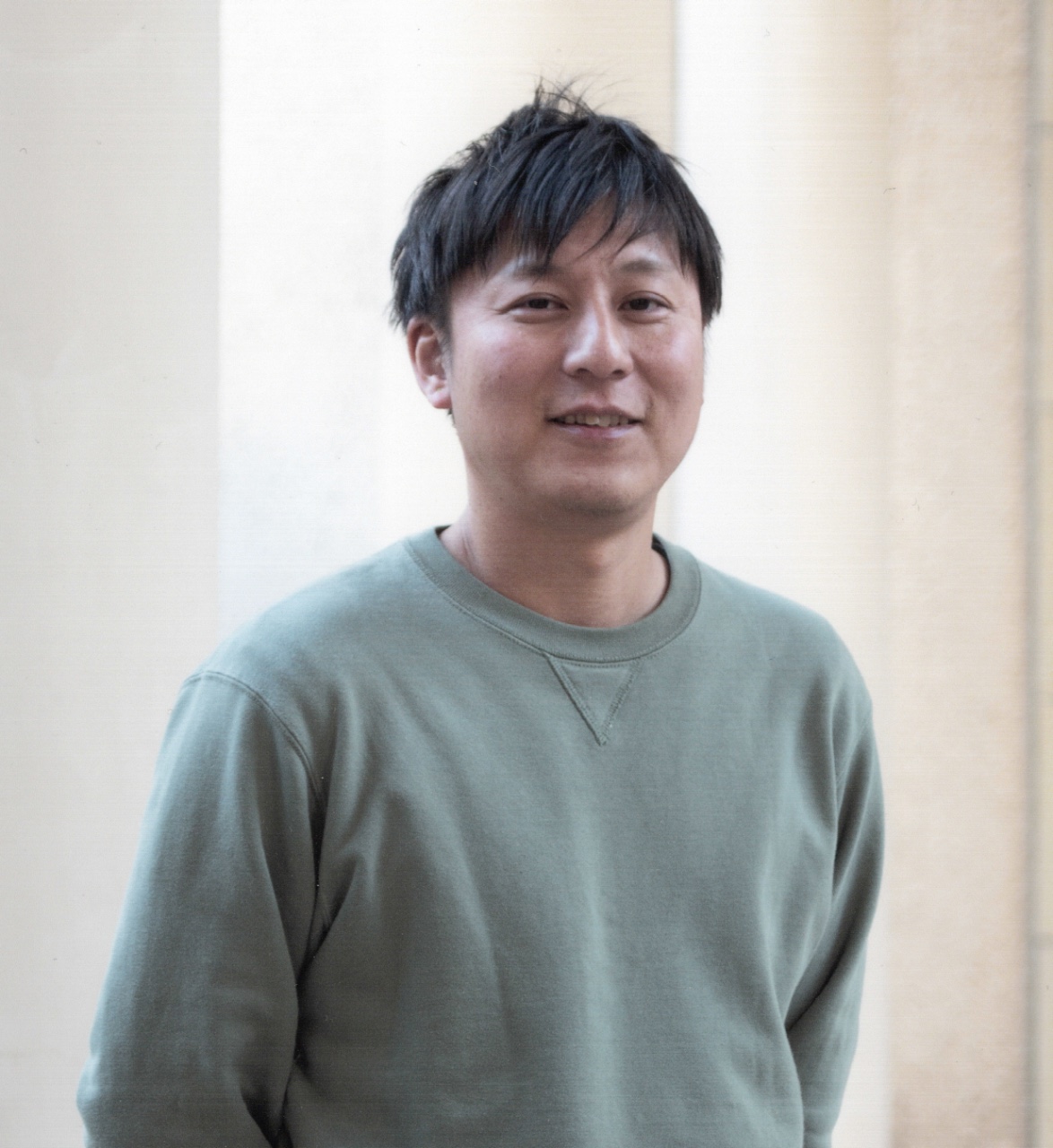
直後の支援から長期的な支援まで
災害直後には、緊急的な活動が求められています。物資配布や避難所環境の整備など、命を守る活動が重視されます。一方で、直後だけではなく息の長い支援も必要です。災害後の避難生活は長期化してしまうことも少なくありません。ハード面ではなく心のケアなどのソフト面の支援も重要になってきます。また、生活再建や復興まちづくりに向けた地域での話し合いなどのサポートも必要になります。
私たちは、これまで直後から支援活動をおこないながら、復興までの息の長い支援をおこなってきました。災害直後から支援を開始することで、地域の方々との信頼関係を築き、復興の道筋を共に描くことを大事にしています。
現在は、2024年能登半島地震、能登半島豪雨災害の支援も継続しています。
こちらの支援もぜひご協力をお願い致します。
被災者一人ひとりに向き合って
特に、その時々の被災地の状況に合わせて柔軟な支援を行うことを心がけています。何よりも、被災した方々一人ひとりの声に耳を傾け、一人ひとりの状況に合わせた支援を行うことにこだわっています
特にソフト面での支援活動を得意にしています。
これまで、足湯ボランティアによる心のケアや専門家と連携した法律相談会、避難所や仮設住宅でのお茶会、復興のための住民会議のサポートなどをおこなってきました。

息の長い支援のためのご協力をお願いします!
ご支援はさまざまな形でおこなっていただくことができます。プロジェクトへの寄付だけでなく、被災地NGO恊働センターへの継続的なマンスリーサポーターとしてのご支援、賛助会員としてご支援いただくことも可能です。
多くの皆様のご協力をいただきながら、被災した方、一人ひとりの生活再建をしっかりと支えていきますので、ぜひご協力をよろしくお願いします。

連携団体:CODE海外災害援助市民センター
今回の支援活動は、姉妹団体のCODE海外災害援助市民センターと連携して活動をおこなっています。CODE海外災害援助市民センターは、阪神・淡路大震災の経験と知見を活かし、幅広い智恵や能力をもつ企業、行政、国際機関、研究機関、NGOなどを含めた市民の集まる場として2002年1月17日にNPO法人として発足しました。CODEは前身となる阪神大震災地元NGO救援連絡会議の時期も含め、これまで60回以上の救援活動を行ってきました。「最後のひとりまで」の理念を胸に、「寄り添いからつながりへ」人間復興となる救援を実践しています。
Partner organization: CODE Citizens towards Overseas Disaster Emergency
This support activity is being carried out in cooperation with our sister organization CODE , which was established on January 17, 2002 as a place where citizens with a wide range of knowledge and abilities, including corporations, governments, international organizations, research institutions, and NGOs, can gather, based on the experience and knowledge of the Great Hanshin-Awaji Earthquake. CODE has conducted more than 60 relief activities, including the time of its predecessor, the Great Hanshin Earthquake Local NGO Relief Liaison Conference. With the motto of, "till the last one", CODE has been practicing relief activities that lead to human recovery, from "leaning close to others" to "connecting with others".

被災地NGO恊働センターの活動
■現在の復興支援活動
東日本大震災支援/熊本地震/2018年西日本豪雨/2019年8月佐賀豪雨/2019年台風19号/2020年7月豪雨/2021年8月豪雨/2022年8月豪雨/2022年台風15号/2023年能登地震/2023年7月豪雨/2024年能登半島地震
■その他の活動
阪神・淡路大震災の際にKOBEは国内だけでなく海外からも多くの支援をいただきました。その時の「ありがとう」「困ったときはお互い様」の思いから災害救援活動がはじまりました。ボランティアは「なんでもありや」「最後の一人まで」をモットーに、様々な被災地の復興に携わりながら地域の自立を支える支援活動を行っています。 海外の災害時には、「CODE海外災害援助市民センター」と連携し、活動を行っています。
また、生きがい・仕事を支える「まけないぞう事業」や、被災地のことや社会のことを勉強する「寺子屋事業」などを実施しています。
平時には地域の防災・減災を推進するため、研修活動や講演活動を行なっています。
■Other Activities
At the time of the Great Hanshin-Awaji Earthquake, KOBE received a great deal of support not only from Japan but also from overseas. Disaster relief activities were initiated out of the gratitude and mutual support at that time. With the mottos of "Nandemoariya (Anything is fine in Japanese Kansai Dialect)" and "Till the last one", volunteers are involved in the reconstruction of various disaster-stricken areas and support activities to help communities become self-reliant. In the event of overseas disasters, we work in cooperation with CODE.
In addition, we implement the "Mamakenai Zou (We will not give up) Project" to support people's motivation to live and work, and the "Terakoya Project" to study about the disaster-stricken areas and society.
ご寄付の使い道
被災地NGO恊働センターは、多くの方々からのご寄付で活動が成り立っています。
いただいたご寄付は、被災地支援活動、災害に備える防災・減災の活動、啓発活動、ネットワークを広げる事業などに使用させていただきます。特定の災害へのご寄付をご希望の場合は、決済画面の備考欄へその旨を記載(例:西日本豪雨災害)ください。
息の長い支援活動を続けていくためには、引き続き暖かいご支援をどうぞよろしくお願いします。
マンスリーサポーターへのご登録は→コチラ
How Your Donations Are Used
The NGO Center for Disaster Area NGO Cooperation is supported by donations from many people.
Donations will be used for disaster area support activities, disaster prevention and mitigation activities, educational activities, and networking projects. If you wish to make a donation for a specific disaster, please indicate so in the remarks column on the payment screen (e.g., "West Japan Torrential Rain Disaster").
We would appreciate your continued warm support in order to continue our long-lasting support activities.
To register as a monthly supporter, click here.