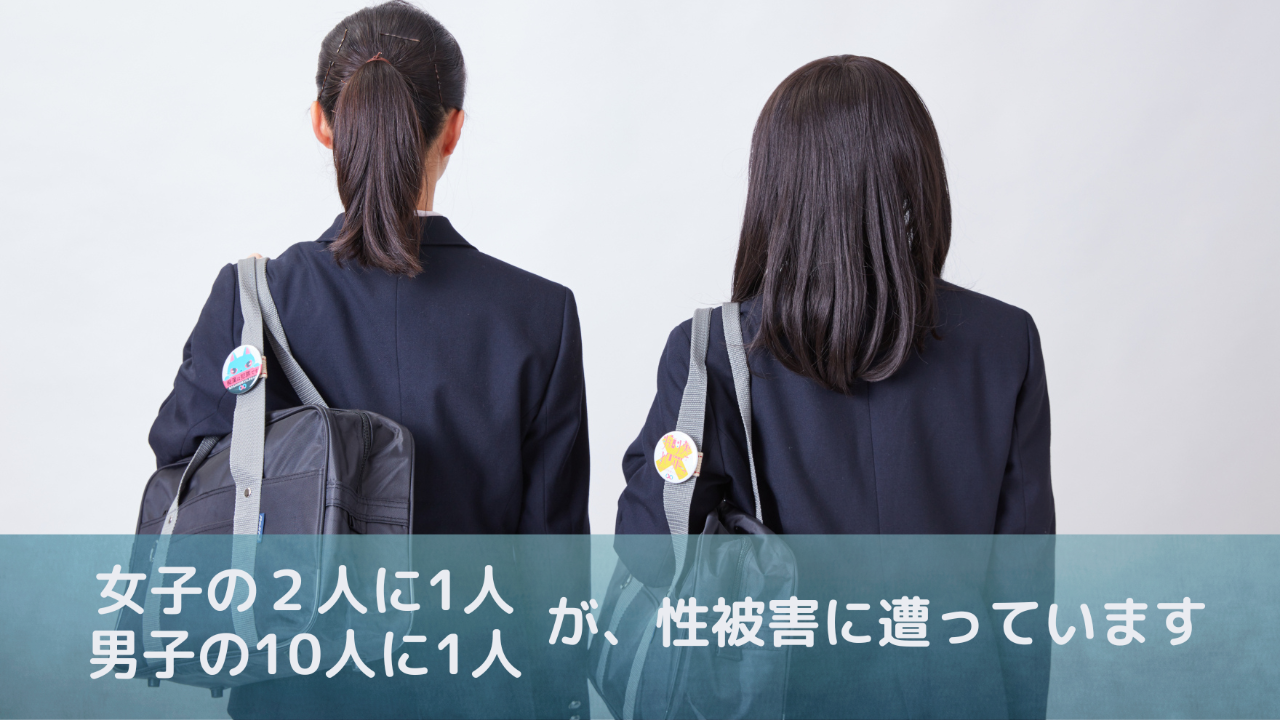■アナウンスの一言が突き刺さった瞬間
私がこのニュースを知ったのは、Xのポストでした。
「今朝の山手線、痴漢行為をした犯人が線路に逃げ込んだとアナウンスしてた」という投稿があり、検索したら複数の同様ポストがあったから、これはデマではないと確信できました。
WEBニュースになったのは翌日。
けれど、あのポストを見た瞬間、私は衝撃を受けました。
「痴漢行為をした犯人が線路内に逃げ込んだため、列車の運転を見合わせています。」
この一言を、公共のアナウンスとしてはっきり流した。
それだけで、社会の空気がひとつ動いたように感じました。
これまでなら「人が線路に立ち入りました」「安全確認のため停車しています」とだけ伝えられてきた。
でも今回は、明確に「痴漢行為をした犯人」と言った。
この違いはとても大きい。
社会がようやく、被害者ではなく加害者に責任を問うフェーズに入った証拠です。
■「痴漢もお客様ですから」と言われた時代
1980年代、まだ「痴漢は犯罪」というポスターさえなかった頃。
大阪地下鉄、御堂筋線で起きた痴漢事件をきっかけに、「性暴力を許さない女の会」が立ち上がりました。
彼女たちは鉄道会社に、痴漢撲滅の啓発ポスターを掲出してほしいと要望した。
けれど、ある鉄道会社から返ってきた言葉は「痴漢もお客様ですから」。
その話を、私は当時活動していた方々から直接聞きました。
だから、山手線の車内で「痴漢行為をした犯人が線路に逃げ込んだ」とアナウンスされたことが、どれほど画期的か、心から驚いたんです。
ほんの数十年前までは、被害者が痴漢にあったと訴えることさえ「迷惑」とされていた。
それが今、鉄道会社自らが「痴漢行為」という言葉を公に使い、被害者ではなく加害者の行動を問題視する。
これは社会が少しずつ成熟してきた証です。
■「犯人ではなく容疑者では?」という声に
ポストに対しては「この段階では犯人じゃなくて容疑者でしょ」という意見もありました。
その指摘は、たしかに正しいです。
報道では、逮捕前に「犯人」と断定する表現は避ける。
私もそれは理解しています。
だけど、痴漢事件のニュースが出るたびに「どうせ冤罪だ」「女性が嘘をついている」と言うのを目にします。
「容疑者」と「犯人」の区別には厳密なのに、「冤罪」という言葉は軽く使う。
その矛盾に、私は強い違和感を覚えます。
「冤罪」という言葉は、本来、有罪判決が確定したあとに無実が証明されたときに使う言葉です。
逮捕された段階でも、通報された段階でも「冤罪」とは呼びません。
ことばの正確さを求めるなら、どちらの場面でも同じ基準で考えてほしい。
そして何よりも、「冤罪」よりはるかに多い “実際に起きている痴漢被害” に、もっと目を向けてほしい。そう思います。
■「線路に逃げた」のは誰だったのか
2017年、線路上を走って逃げる男の動画がSNSに投稿されました。
それをきっかけに、同様の事件が十数件、ニュースで報じられています。
京王井の頭線で女子大生の下半身を触って逃げた慶應大生。
新宿駅で盗撮し、事情聴取中に線路に逃げた男。
武蔵野線で女子高生を触り、駅員に引き渡されそうになって逃げた会社員。
埼京線でわいせつ行為をして線路に飛び降りたタクシー運転手。
いずれも逮捕され、容疑を認めています。
つまり、線路を走って逃げるのは「冤罪で追い詰められた人」ではなく、現行犯で捕まりそうになった加害者です。少なくとも私は「線路を走って逃げたけど、痴漢はしていなかった」というニュースを聞いたことがありません。
ご存じの方がいたら、ソースをシェアしてほしいです。
■「逃げろ」と言われた時代から、「逃げるな」と言われる時代へ
2007年に上映された映画『それでもボクはやってない』がヒットした直後の時代を覚えていますか。
当時はテレビでも弁護士が、「痴漢に間違われたら線路を走ってでも逃げろ」と言っていました。
でも今は、法曹界でも「逃げること自体が危険で、さまざまなリスクを伴う」と言われるようになっています。
「痴漢を疑われて逃げる」という行為が、どれほど多くの人を巻き込み、どれだけ社会的に重い意味を持つのかが、ようやく理解され始めた。
その変化を象徴するのが、今回のJRのアナウンスだったと思うのです。
■被害者を疑う社会から、加害者の責任を問う社会へ
もし無実なら、逃げる必要はありません。と、弁護士が言っています。
逃げるという行動自体が、自らの罪を認めているようなものです。
被害者が声を上げたから電車が止まったのではなく、逃げた加害者が止めた。
迷惑をかけたのは誰か。
その視点を、もう一度社会全体で見直す必要があります。
今回のアナウンスは、その転換点でした。
被害者の勇気を守るために、公共交通が「加害行為」を明確に言葉にした。
それは長い年月をかけて積み上げられてきた運動の成果でもあります。
私たちはいま、社会の意識が確実に変わりつつある瞬間に立っています。
被害者を疑う社会から、加害者の責任を問う社会へ。
その流れを止めないために、これからも声を上げ続けたいと思います。