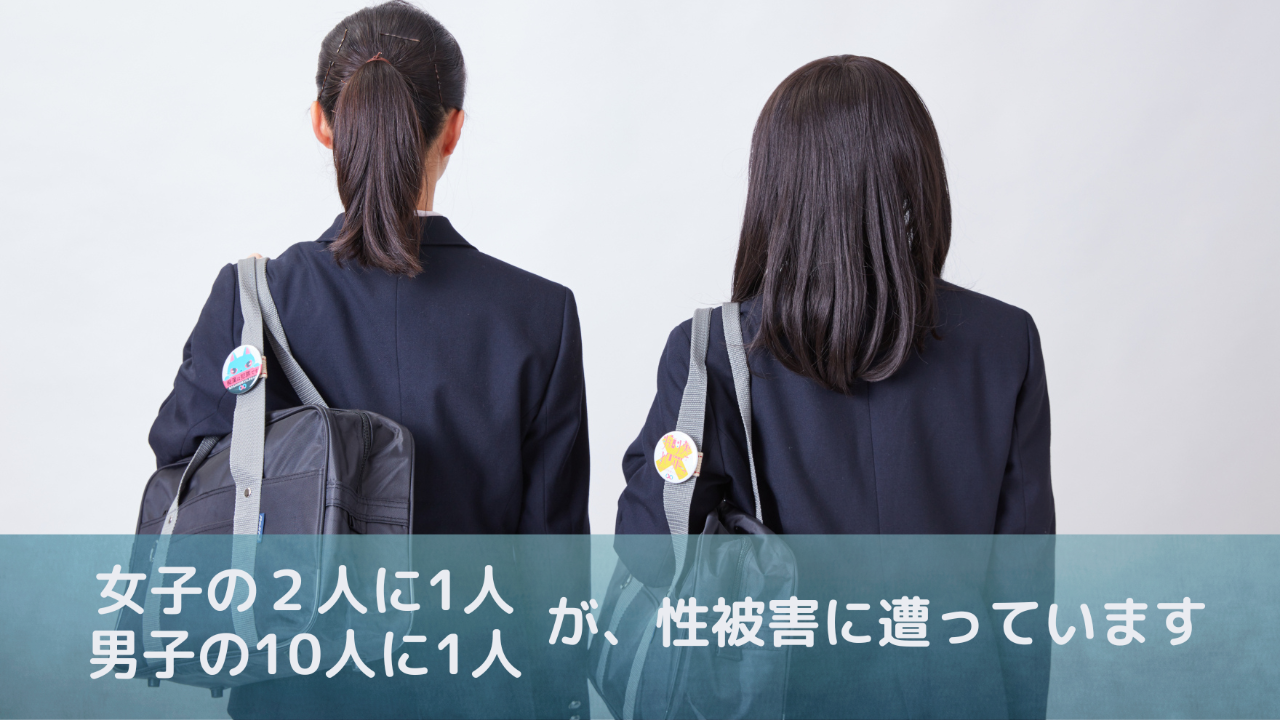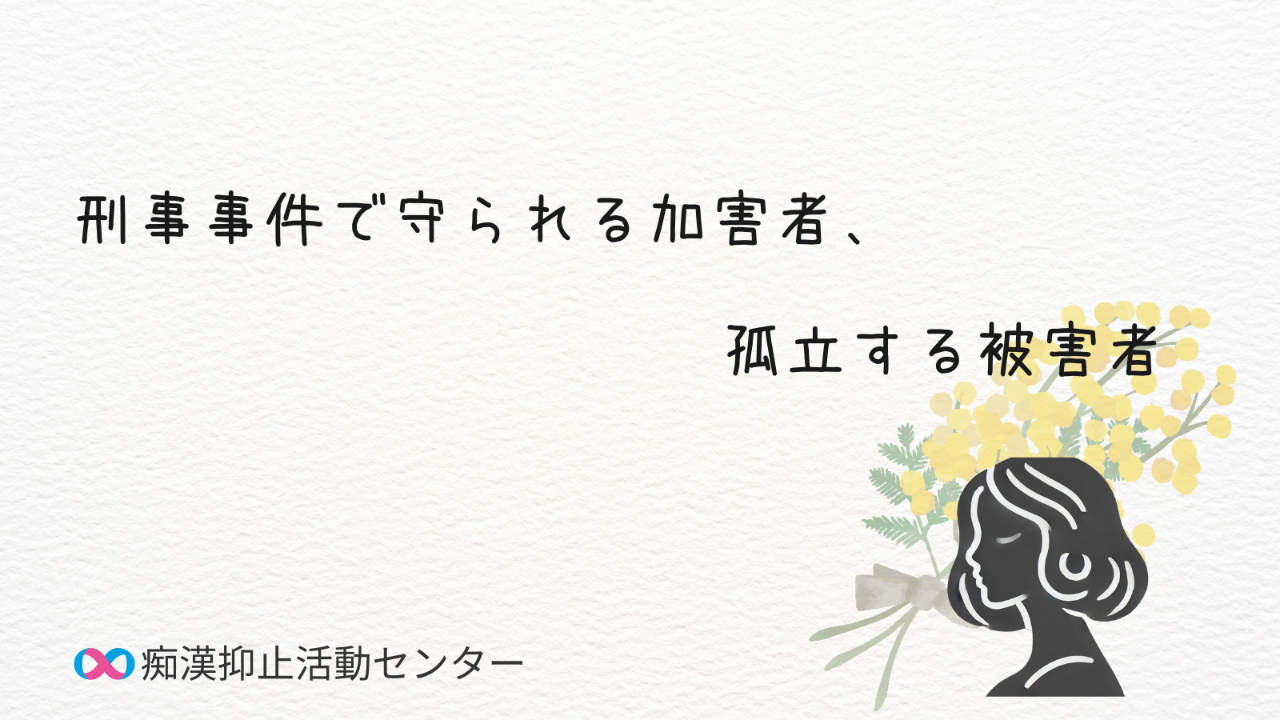
一般的な刑事事件の流れ
まず一般的な刑事事件は次のように進みます。
- 逮捕
警察が捜査を行い、証拠や状況から犯罪の可能性が高いと判断した場合、容疑者を逮捕します。逮捕された容疑者は、最長48時間以内に検察庁へ送致されます。 - 勾留
検察官が勾留を裁判所に請求し、裁判所が認めると、容疑者は最長20日間拘束されます。この段階から弁護士を依頼でき、資力がなければ国選弁護人が選任されます。これは憲法で保障された権利です。 - 起訴・不起訴の判断
検察官は集めた証拠や供述を基に起訴するかどうかを判断します。不起訴となれば裁判は開かれません。 - 刑事裁判
起訴されると刑事裁判が始まります。検察官が有罪を立証し、弁護士が被告人を弁護し、裁判官が有罪か無罪か、刑罰の内容を決めます。
痴漢事件の特徴
痴漢事件には、一般の刑事事件とは異なる特徴があります。
多くの痴漢事件は 現行犯逮捕 です。被害者本人、駅員、周囲にいた人がその場で加害者を確保するケースが多く、現場対応が先行します。もちろん、防犯カメラの映像などから、後日の捜査で逮捕に至るケースもあります。
逮捕後は、一般的な事件と同じ流れで検察に送致され、勾留・起訴判断へと進みます。
昔は痴漢事件でも逮捕されたらそのまま勾留されることが多かったそうです。でも今は、身元や職場が安定していて逃亡のおそれがない場合、勾留されずに釈放されるケースも増えています。
これは人権の観点から必要以上の身柄拘束を避ける流れでもありますが、被害者にとっては「加害者にまた会ってしまうかも」「逆恨みで危害をくわえられるかも?」「電車から家まであとを付けられたらどうしよう」などという不安や恐怖につながります。
痴漢事件では、不起訴になる割合が高いことに注意が必要です。
痴漢は、法律上の扱いが2種類に分かれています。痴漢の中でも悪質なものが不同意わいせつ罪、そこまで悪質ではないものが迷惑防止条例違反になります。具体的なイメージとしては、服の中に手をいれたら不同意わいせつ罪、服の上から触ったら迷惑防止条例違反という感じです。
例えば、不同意わいせつ罪(旧・強制わいせつ)では60%以上が不起訴、迷惑防止条例違反も約3割が不起訴とされています。
つまり、どちらも性被害であることに変わりはないのですが、適用される法律の種類と扱いの重さに違いがあります。
逮捕されたあと、加害者はできるだけ穏便に済ませようと、弁護士を雇って被害者と示談交渉に入るケースが少なくありません。
示談が成立すれば「被害感情の回復」や「情状酌量」として考慮され、検察官が不起訴を選ぶ大きな要因になります。実際、起訴直前に示談が決め手となって不起訴になることも多いのです。
一方で、被害者には基本的に弁護士がつきません。必要を感じたら、自己資金で手配するしかないのです。
調書を取る段階で何度も同じことを繰り返し聞かれることで、自分が細かいところを思い出せなくなって、発言に自信がなくなり食い違いがでてくると「証言に一貫性がない」と判断されるリスクもあります。
そして最終的に、起訴するかどうかを決めるのは検察官です。
加害者と被害者の守られ方の差
私がここで強調したいのは、加害者と被害者の「守られ方の差」です。
加害者は逮捕直後から弁護士を依頼でき、資金力がなくても勾留認められたり起訴された段階で国選弁護人がつきます。つまり「法律のプロがそばにいる」状態が早い段階から整います。
一方で被害者はどうでしょうか。検察官は「公益の代表」として社会秩序の維持のために働く存在であり、被害者個人の利益を守る立場ではありません。
痴漢抑止バッジ考案者の殿岡たか子さんも、痴漢を捕まえて裁判を行った一人です。
たか子さん自身、加害者を逮捕して裁判まで行った経験から、まさに「弁護士がほしい!ほしかった!」と、当時を振り返っています。
当時、彼女は高校生だったので、加害者側の弁護士とたか子さん母親の間で示談交渉が行われたそうです。たか子さんが示談を断固拒否したため、裁判になりました。
検察官は被害者に寄り添ってくれるわけでも法律的なアドバイスをしてくれるわけでもありません。法律のプロと一市民が交渉をするのですから、法律知識の有無による力の不均衡は明らかです。
現状では、被害者に弁護士が自動的につく仕組みはなく、被害者(やその周囲の方が)自力で味方になってくれる弁護士を探すしかないのです。
しかし「痴漢 弁護士」と検索すると、出てくる情報は加害者弁護を専門にする事務所ばかりです。「被害者からの相談は受けません」と明記する事務所すらあります。
こうした現実の中で、被害者は事件の初期段階から法律のプロである加害者弁護士と一人で向き合うことを迫られます。
加害者は弁護士に守られ、被害者は孤立する。このアンバランスが制度の大きな課題だと私は考えています。
被害者が使える制度
もちろん、被害者の方にまったく手がないわけではありません。
- ワンストップ支援センター:性犯罪や性暴力の被害者が 医療・警察・法律相談などを一か所で受けられる窓口です。
- 被害者支援弁護士制度:各地の弁護士会ごとに「犯罪被害者支援委員会」を置いています。被害者からの相談を受け、刑事手続きに詳しい弁護士を紹介してくれます。
- 法テラス:資金力要件を満たせば、無料相談や弁護士費用の立替制度を利用できます。
- 被害者参加制度:殺人や強制性交等など重大事件では、被害者が裁判に参加し意見を述べられます。国費で「被害者参加弁護士」が付く場合もあります。ただし痴漢のうち、条例違反に当てはまるケースでは対象外のことが多いのが現実です。
- 被害者支援室:検察庁や警察に設置され、手続きや流れを説明してくれます。
こうした窓口や制度は確かに存在します。ワンストップ支援センターや法テラスなどは事件直後から相談できますし、弁護士会の被害者支援制度や警察・検察の支援室も入口になってくれます。
ただ、裁判に直接関われる「被害者参加制度」や「国費で弁護士が付く制度」は起訴後にしか使えません。
そのため、事件直後から裁判までのあいだ、被害者が継続的に寄り添ってもらえる仕組みはまだ十分とは言えず、大きな空白が残っているのです。
2025年9月5日の朝日新聞によると、犯罪被害者やその遺族らに対し、弁護士が公費で包括的な支援をする制度が、来年1月13日から始まるそうです。
記事には、「制度が始まれば、日本司法支援センター(法テラス)と契約した弁護士が、被害届や告訴状の作成・提出▽捜査機関への同行▽加害者側との示談交渉▽裁判傍聴の付き添い▽民事訴訟の提起▽犯罪被害者等給付金の申請▽メディア対応――などを公費で請け負う」とあります。
ただし、公費を使うには一定の資力要件があります。それでも被害者の立場に寄り添う方向に制度が変わりつつあるのは、喜ばしいと思います。
まとめ
私が当初のポストで伝えたかったのは、加害者には逮捕直後から弁護士がつけられます。被害者は自分で探さない限り、寄り添ってくれる専門家がいません。しかも、被害者に寄り添ってくれる弁護士を見つけるのが難しい。そのことが不起訴の多さや、被害者の孤立感につながっているのではないでしょうか。だから、被害者にも事件直後から弁護士をつけてほしい。 ということです。
言葉足らずで、私の伝えたいことが正しく伝えられませんでした。
私は声を大にして言いたいのです。
「被害者は、孤立しなくていい」
「ワンストップ支援センターや、法テラスなどの制度を使っていい」
まずは制度を知ること。そこから支援の輪を広げていくことが必要だと私は考えています。