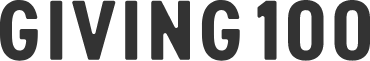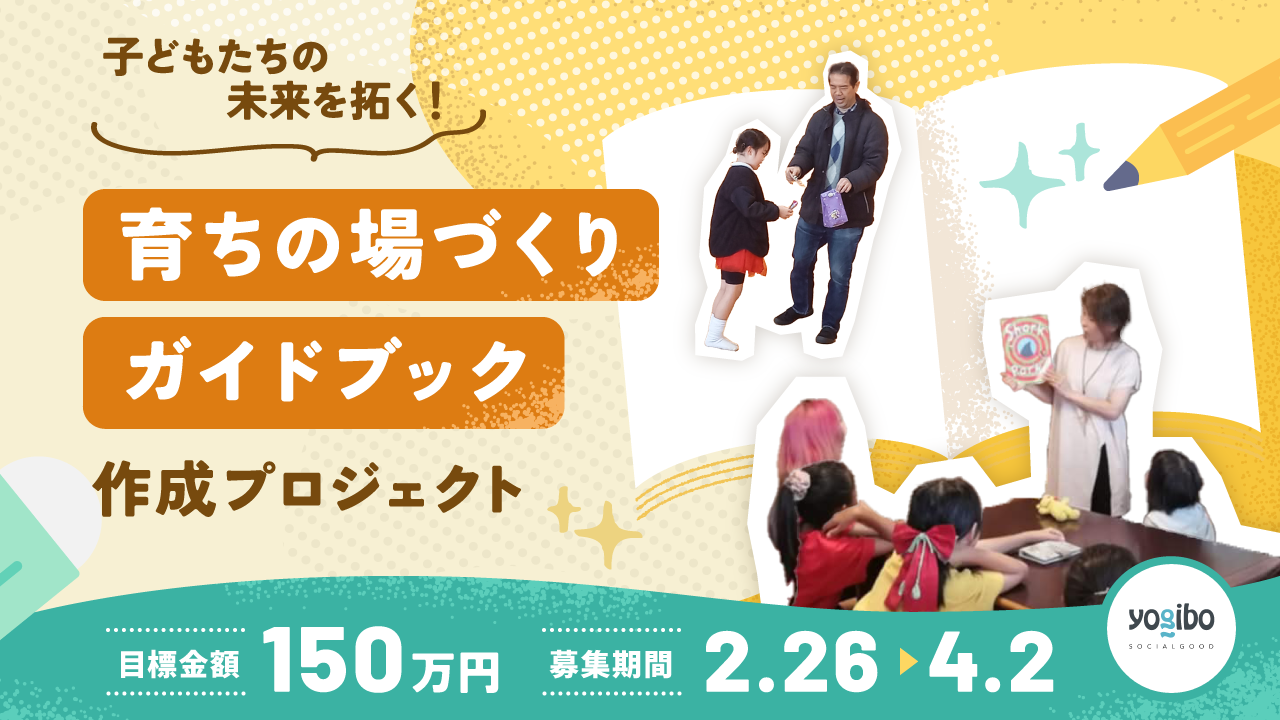「やったー!」「おれ、ぎりぎり!」漢字検定の結果が返ってくるたび、子どもたちの間には様々な感情が溢れます。瀬戸ツクルスクールでは、学習環境の保障としてeboardという学習サイトのアカウントを一人ひとりに付与し、さらに年数回、希望者が検定を受けられる機会を設けています。
しかし、そもそも評価とは何なのでしょうか?そして、それは本当に必要なものなのでしょうか?瀬戸ツクルスクールには、いわゆる「先生」という役割の人がいません。そのため、従来の学校のような評価は存在しません。また、通知表もありません。
それでも、子どもたちの中には「自分の力を試したい!」という気持ちを持つ子が一定数います。彼らにとって、検定は一つの目標となり、モチベーションを高めるきっかけとなります。私たちは、そのような子どもたちのために、学校としてできる範囲の環境を整えることが大切だと考えています。
日本における評価は、大きく分けて「ジャッジメント(判断)」と「アセスメント(評価)」の2つに分けられます。ジャッジメントは主観的な評価であり、アセスメントは客観的な評価です。現在の学校教育はジャッジメントに偏りがちですが、私たちは子どもの成長にはアセスメントが重要だと考えています。
特に、まだ枠の決まっていない子どもたちにジャッジメントを行うことは、可能性を狭めてしまうことになりかねません。しかし、自己成長のための自己理解として、客観的なアセスメントは必要です。検定は、そのための客観的な資料の一つとなります。
もちろん、検定はあくまでオプションに過ぎません。瀬戸ツクルスクールでの学びの本質は、日々の生活の中での変化のプロセスにあります。しかし、子どもたちが「やりたい!」と思ったときに、そのモチベーションを高める環境を提供することは、学校の重要な役割ではないかと考えています。
学習動機づけ理論における「目標を持つ」という原理原則に基づき、私たちは子どもたちの学びを支援します。振り返りは学びにおいて重要であり、アセスメントはその重要な要素の一つです。そして、検定はその具体的な事例の一つと言えるでしょう。
一方で、学校の通知表はジャッジメントに偏りがちであり、子どもの可能性を制限してしまう可能性があります。また、主観的な評価が客観的な評価として捉えられがちであり、進路選択にも大きな影響を与えます。
通知表を出す出さないは校長裁量で決められるということからも、その重要性は絶対的なものではないのかもしれません。しかし、保護者の方々は通知表に一喜一憂し、振り回されてしまっている現状もあります。
私たちは、評価の本質を見直し、子どもたちの学びと成長を支援したいと考えています。瀬戸ツクルスクールでは、約20名の子どもたちがそれぞれのペースで検定に挑戦しています。彼らの学びを支えるために、私たちはこれからも様々な取り組みを続けていきます。
金額3,000円 |
金額5,000円 |
金額10,000円 |
金額30,000円 |
金額50,000円 |
金額100,000円 |
金額3,000円 |
金額5,000円 |
金額10,000円 |
金額30,000円 |
金額50,000円 |
金額100,000円 |