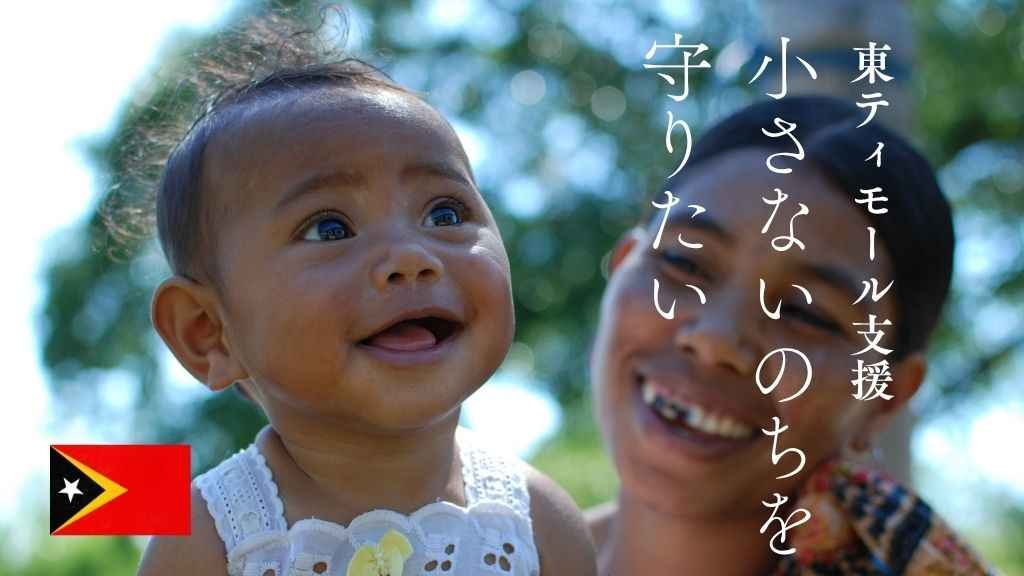こんにちは!日本の皆さん、お元気ですか?いつも皆さまの多大なご支援に感謝しています。
私の名前はリマ・エヴァリアンティといいます。私は2019年4月からシェアのスタッフとなり、現在は医療者にアプローチをする活動を担当しています。それまでは東ティモールのクリニックで助産師として働いていました。
今年7月、「清潔で安全な分娩トレーニング」を国立医療研修所(以下、INS)と共同で実施しました。
このトレーニングで感じたことを、今回のブログで皆さんと共有したいと思います。

目次
トレーニングの目的は??
「清潔で安全な分娩」とは、医療施設での分娩または自宅でも助産師など医療者が介助する分娩を指し、トレーニングでは通常の分娩介助をするための基本的な知識や技術が提供されます。私たちシェアが今年3月から始めた「母子保健サービス活性化」事業(※1)の活動の一つです。保健センターに勤務する医療者たちが正確な技術と自信をもって母親たちに分娩介助のサービスを提供できるようになることを目的としています。
医療者11名(助産師4名、医師7名)が参加し、彼らを事業の中でフォローアップしていくために、シェア職員からは私(助産師)と看護師のスタッフ1名がオブザーバーとして参加しました。医療者たちは、トレーニングの中で出産の過程と必要なケアについて学びました。

※1:この事業は外務省日本NGO連携無償資金協力の補助金と皆様からのご寄付で実施しています
分娩介助実習
トレーニングは座学のみではなく、保健センターや国立病院での実習も含まれています。私も首都ディリにある国立病院の実習に参加しました。
実習で、最初にオブザーバーとしてついた母親は、なんとまだ18歳で、陣痛から出産までに2時間を要しました。初産の彼女は不安を感じていたので、担当の助産師が楽しい話をしたり、どのように息むかを伝えたり、精神面のケアをサポートしていました。母子ともに健康で、私がオブザーバーを担当していた助産師も、無事に分娩介助を終えることができ、安心しました。
分娩後は、子どもの身体状態と呼吸の確認を行い、産後の予防接種、母乳のあげ方などを母親に指導していました。生まれてくる命に一番はじめに接する助産師の仕事はやはり重要だと思いました。

トレーニング後に大切なこと
トレーニングに参加し、シェア職員としてとても誇らしかったことは、参加した医療者たちが最初は不安気だったのに、最終日には彼らが自信に満ちていたことです。そして私に対して、「これから私たちは自分たちの仕事場で、地域の人々に対して良い分娩介助をしていきます!」と決意表明をしてくれたことです。
他にも、「このトレーニングはとても有意義で貴重な機会だから、自分たちの仲間にも是非参加して欲しい」という声が聞こえました。参加した医療者にとって何が課題で、それらを解決するためにどんなトレーニングを実施すべきなのか、をINSと共にしっかり話し合えたことも良かったのだと思います。

今回トレーニングに参加した医療者が知識と技術を忘れず、正しい分娩介助サービスを継続して提供し続けるには、私たちシェアからのフォローアップが大切だと感じています。
母親たちが施設分娩を利用しない理由は様々です。施設まで遠い、お金がなくて交通費が払えない、など。でも、母親たちが施設分娩をしたい、と思えるような保健医療サービスの提供は欠かせません。そのために、まずは医療者が彼女たちに寄り添い、仲の良い友だちのような存在になって欲しいです。お母さんと子どものことを考え、必要な情報を提供し、カウンセリングをしてあげられるような…。そうすることで、彼女たちも医療者に信頼を寄せて施設利用をしてくれるようになると思います。
今回、オブザーバーとしてトレーニングに参加し、私も知識と技術を得ることができましたので、今後の医療者へのフォローアップを頑張ろうと思います!