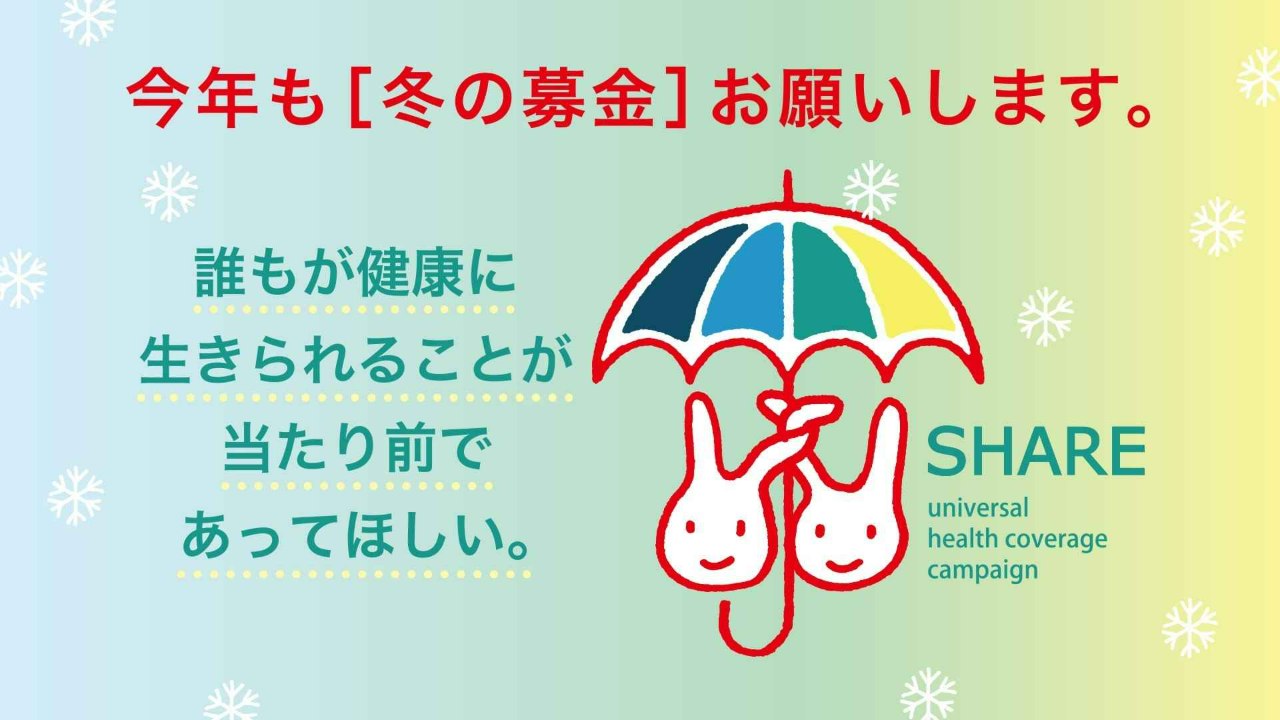誰もが健康に生きられることが 当たり前であってほしい。
カンボジア
《栄養と知識を届け、すべての子どもが健やかな毎日を過ごすように》
私たちはプレアビヒア州の農村地域にて、女性子ども委員会や保健ボランティアと一緒に子どもたちの健康を見守る活動を続けています。3 ヶ月に1 回行う子どもの健康増進活動では、体重や身長の記録を取り、栄養状態を確認。離乳食教室の開催や、栄養や衛生についてアドバイスを行っています。ある母親は『バランスの良いご飯をつくるようになったことで子どもたちが病気にかかりにくくなりました』と喜びの声を寄せてくれました。皆さまのご支援で、より多くの家庭に健康の知識とサポートを届けていきたいと考えています。

東ティモール
《学びと想いが重なり、すべての母子が守られるように》
山あいの小さな診療所で働く助産師さん。新人として知識や技術に不安があり、お産を受け入れられず妊婦を街の病院へ送り出していました。私たちは、医療者が国の研修機関で学べるよう支援しています。研修を経て自信を得た彼女は、今、自らの診療所でお産を受け入れています。小さなソーラーランプを手に「この灯りで新しい命を迎えるの」と笑う彼女。ひとりの助産師の成長が、母と子の命を支える力となり、地域を変えていく。それが、私たちの目指す未来の形です。

日本
《医療通訳が言葉をつなぎ、誰もが安心して暮らせるように》
東京都内において、保健医療福祉従事者が母子保健サービスを提供する際に医療通訳派遣を行っています。この取り組みにより、保健医療福祉従事者と外国人妊婦や母親が、円滑にコミュニケーションがとれ、関係性が深まり、子どもの体調不良など困ったときに保健センターに相談していいと認識してくれるようになりました。こうしたうれしい変化に、保健師さんたちも医療通訳の大切さを実感していると話してくれています。言葉の壁を取り除き、適切な情報が提供されることで、母子保健サービスへのアクセスが着実に進んでいると感じています。

代表者メッセージ
<ご挨拶と年末年始募金のお願い - UHCキャンペーンに寄せて- >
プライマリー・ヘルス・ケア(PHC)とユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)
PHCとは、健康であることを基本的な人権として認め、全ての人が健康になること、そのために地域住民を主体とし、人々の最も重要なニーズに応え、問題を住民自らの力で総合的かつ平等に解決していくアプローチです。1978年、WHOとUNICEFが中心となり、国際会議を開催しました。134ヵ国の政府代表と67の国際機関・NGOが参加し、「2000年までにすべての人に健康を」として、アルマ・アタ宣言として承認され、その後の国際保健のイニシアティブとして、世界中で実践されてきました。シェアは、このPHCを理念として、長年、カンボジア、タイ、東ティモールそして日本において活動を実施してきました。
一方UHCは、2015年からのSDGs「持続可能な開発目標」の一つである、「目標3:すべての人に健康と福祉を」の中で基本的な概念とされているものです。「全ての人が適切な予防、治療、リハビリ等の保健医療サービスを、支払い可能な費用で受けられる状態」を指し、基本的な概念はPHCと同じものと言えます。ただ、PHCでは基本的な保健医療サービスの提供を目標にしていましたが、UHCでは、脳血管疾患や心臓病といった非感染性疾患も対象に含めた保健医療サービスの提供や、サービスの質を上げることが目標にされたことが大きな違いです。また、PHCでは、地域のリソースを用い、できるだけ、費用がかからない中での保健医療サービスの提供を目標としていましたが、UHCでは、国や地域として、責任をもってヘルスへの費用を負担することが目標とされています。
現在シェアは、カンボジア、東ティモール、日本において、母子保健を中心とした活動を実施していますが、いずれの事業でも、基本的には、UHCを目指しているものです。シェアは、十分に保健医療サービスを受けられない人々のための支援を、カンボジア、東ティモール、 日本、そして新しい活動国において、これからも継続・拡大していきたいと思っています。
是非、皆さんのご支援を途上国の困難な状況にある人々に届けさせてください。
今年もシェア冬の募金へのご協力を、よろしくお願いします。
特定非営利活動法人 シェア=国際保健協力市民の会
代表理事 仲佐保

寄付金の使い道について
いただいたご支援は、シェアの「いのちを守る人」を育てる活動のために大切に使わせていただきます。