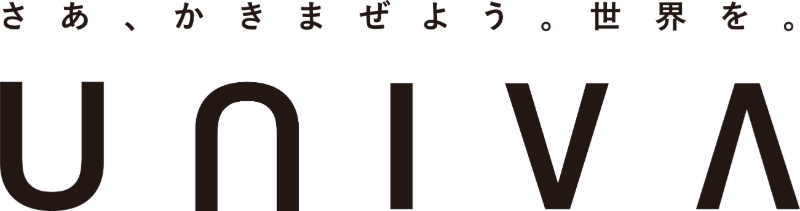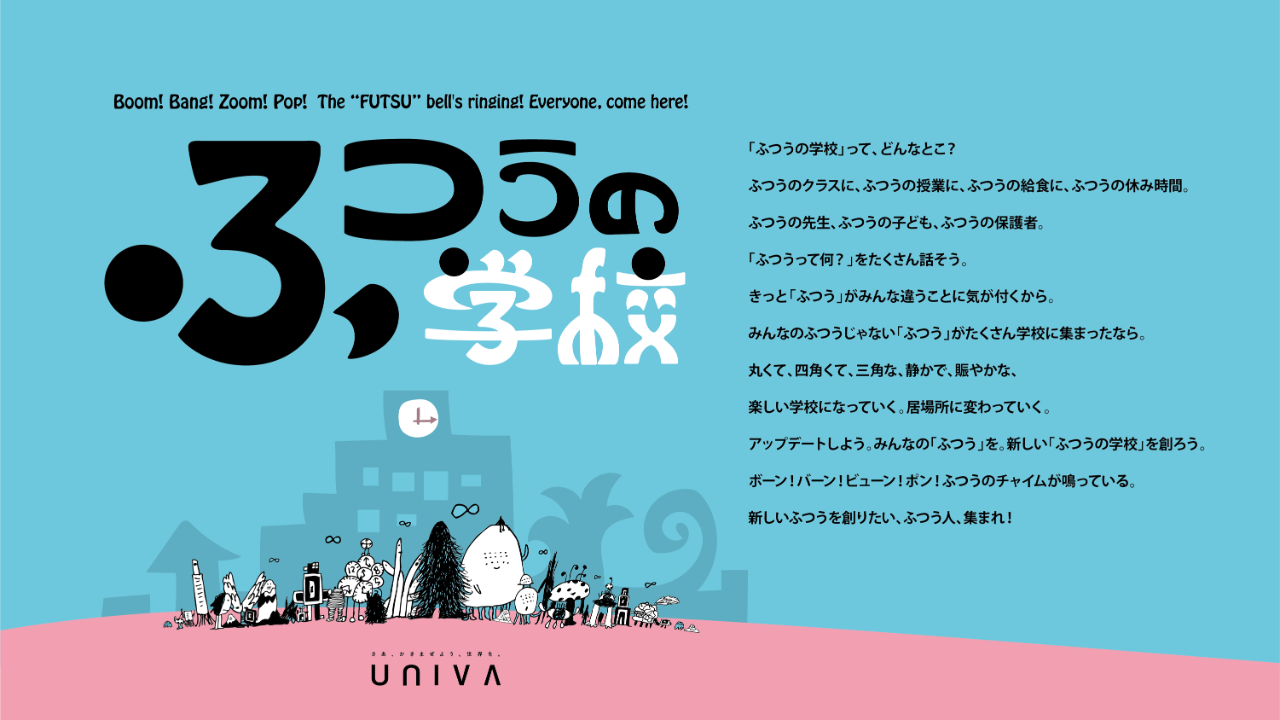活動内容の概要
「“ふつう”に合わせるのではなく、“ふつう”を変えることができるんだと思った」
UNIVAが先生たちと共に開発した「ふつうアップデート」授業後の中学生の感想です。
自分と価値観が異なる人、背景が違う人、ちょっと嫌だな、と感じる人。世の中には多様な人がいます。
学校教育の役割の一つは、異なる事情や背景を持つ人と共存する方法を学ぶことです。
一方で、不登校状態にある子、特別支援学級や特別支援学校に在籍する子どもたちの数は年々増加し、今の”ふつう”の学校が多くの子どもにとって居心地の悪い場所になっていることを危惧しています。
「”ふつう”に合わせるのではなく、”ふつう”を変えていくことができる」
誰もがそう思えれば、今の学校はすべての子どもにとって安心できる場になるのではないでしょうか。
子どもたちが、学校や自治体と共に学校における”ふつう”をアップデートをした事例をご紹介します。
子どもたちと共に学校の”ふつう”をアップデートする
「『夏休みが楽しみ』なのはふつう?」「右利きはふつう?」「『授業中に緊張しない』のはふつう?」
「ふつうアップデート」授業では、子どもたちがそんな問いかけや実際に体験を通して「”ふつう”とはなにか」について考えます。自分にとっては左利きがふつうだけど、世の中は右利き中心にできている...など、身近な事例から、実は一人ひとりにとって”ふつう”はちがうこと、けれど世の中の”ふつう”は決まっていること。自分の”ふつう”と世の中の”ふつう”が一致していたら特に困らないけれど、一致していないと不利で不便であること、世の中の”ふつう”をアップデートすることで困りごとは解決できること、などを学びます。
子どもたちは自身の困りごとや身近な困りごとを、”ふつう”アップデートで解決する方法を考えます。例えば、ある学校では、ドッジボールの”ふつう”のルールのアップデートを考えました。ある学校では、「45分授業は長くて集中しづらいから、15分ずつが良いのではないか」「発表するときに緊張するからぬいぐるみをもって発表するのをOKにするのが良いのではないか」など、授業や学校のルールのアップデートを考えました。その後、実際に学校のルールや環境をアップデートしたケースもあります。
誰かにとっての”ふつう”アップデートが、誰かにとっては障壁になることがあること、同じ困りごとでも人によってアップデートの方法が違うこと、など、実際の体験を通して、異なる”ふつう”を持つ人同士が共存するための具体的方法を考え、子どもたち自身もインクルーシブな学校づくりの担い手となります。
現在、この「ふつうアップデート」授業の指導案や教材を一般公開する準備をしています。
先生たちと共に学校の”ふつう”をアップデートする

「学校をよりインクルーシブな場にしていきたいけれど、何からはじめたら良いかわからない」「多様な子どもたちがいることはわかっているけれど、忙しくて正直それどころじゃない」全国からこのような相談があります。
UNIVAと学校との協働の際は、まず先生たちがどのように学校を変えていきたいか、今の学校の実態はどうなっているか、などをヒアリングします。学校によって実態も先生たちの思いも異なるため、その学校の先生方にとって無理のない範囲で、できそうなところから改革をスタートします。例えばある学校は、通常の学級の先生たちが今すぐにできる子どもの多様性を踏まえた接し方や授業づくりのちょっとしたコツを共有するところから始めました。他の学校は、まずは多様な先生たちが働きやすいインクルーシブな職場づくりから始めました。そのほかにも、学校規模で取り組むポジティブ行動支援を取り入れる学校、授業づくりを変える学校など...学校によって具体的な取り組み内容は様々です。
ある学校では、インクルーシブ教育に関心を持つ先生たちが、「インクルーシブ有志の会」を結成し、チームにわかれ、インクルーシブ教育を推進する活動を始めました。「教材チーム」は、通級や特別支援学級で使用している教材を職員室に展示し、通常の学級においても使えるような環境整備をしました。「安心コミュニケーションチーム」は職員室内に掲示板をつくり、先生同士がコミュニケーションが促進されるための工夫をしました。「授業のインクルーシブ化」チームは、子どもたちが授業の中で学び方や教材、学ぶペースなどを選択できるような工夫を取り入れていきました。そのほかにも、授業を校内にクールダウンスペースを設置したり... このような活動について、全校研修の場で全体に共有し、それぞれが取り入れていくような取り組みです。UNIVAは定期的に学校を訪問し、先生たちが活動をするなかで感じたモヤモヤや疑問、葛藤について対話をしました。
自治体や国と共に学校の”ふつう”をアップデートする
変化は、学校だけにとどまりません。教育委員会と連携し、インクルーシブな学校づくりのために、どのような政策が必要か、また、先生方のサポート体制はどうあったらよいか、などを共に検討します。
例えば、ある自治体では管理職向けのインクルーシブ教育の研修が実施され、インクルーシブ教育を学校経営の中心に据える動きが生まれました。そのほかにも、社会モデルの授業を実施する学校や自治体同士がお互いに見学をしあったり、実践を共有しあったりする動きも生まれています。インクルーシブ教育に取り組む自治体同士が連携したり学び合ったりできるようなネットワークづくりも開始しています。
UNIVAは、全国のモデル自治体に対して研修/コンサル/政策立案支援を実施しているほか、自治体の方針を策定する委員に就任するなど、さまざまな立場から自治体の変革をサポートしています。
モデル自治体(予定を含む)
・埼玉県戸田市
・東京都狛江市
・大阪府箕面市
・長野県諏訪市
UNIVAメンバーの自治体とのかかわり(抜粋)
・戸田市 インクルーシブ教育戦略官
・箕面市 支援教育充実検討委員会委員
政策と実践の両輪がそろって、初めて社会は変わっていく。現場での変化が政策を後押しし、政策が現場を支える。その両輪を回していくことが、学校の”ふつう”をアップデートしていくことにつながります。
UNIVA理事が委員を務める中央教育審議会「教育課程企画特別部会」では、インクルーシブ教育実現の鍵となる社会モデル・多層型支援の考え方や、それらを踏まえて通常の学級において多様な選択肢を準備することで障壁を解消している具体事例を紹介するなど、実効的な提言を実施。こうした政策提言を通し、次期学習指導要領における「多様な個性や特性、背景を有する子供たちを包摂する柔軟な教育課程」の実現に向けたモメンタム形成を進めています。
UNIVAメンバーの政策とのかかわり(抜粋)
・文部科学省 中央教育審議会 教育課程企画特別部会
・内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム (SIP) プログラムディレクター補
・東京大学 先端科学技術研究センター 社会包摂システム分野 特任研究員
あなたのご寄附が必要です。
多様な子どもたちが、誰もが過ごしやすい学校・社会をつくっていくためには、個人単位の「努力」や「助け合い」だけでなく、「仕組み」を変えていくことが必要です。
UNIVAと学校との共創プロジェクトに、ぜひお力を貸してください。
あなたの力で、みんなの力で、社会を仕組みから変えていきませんか?
ご寄付の使い道
いただいたご寄付は、以下のような使途に使わせていただきます。
・全国の自治体・教育委員会・各地域におけるインクルーシブ教育コーディネーターの育成・支援活動
・インクルーシブ指標や政策に関する、海外のインクルーシブ教育(アメリカ、イタリア、カナダ等)の共同研究の実施