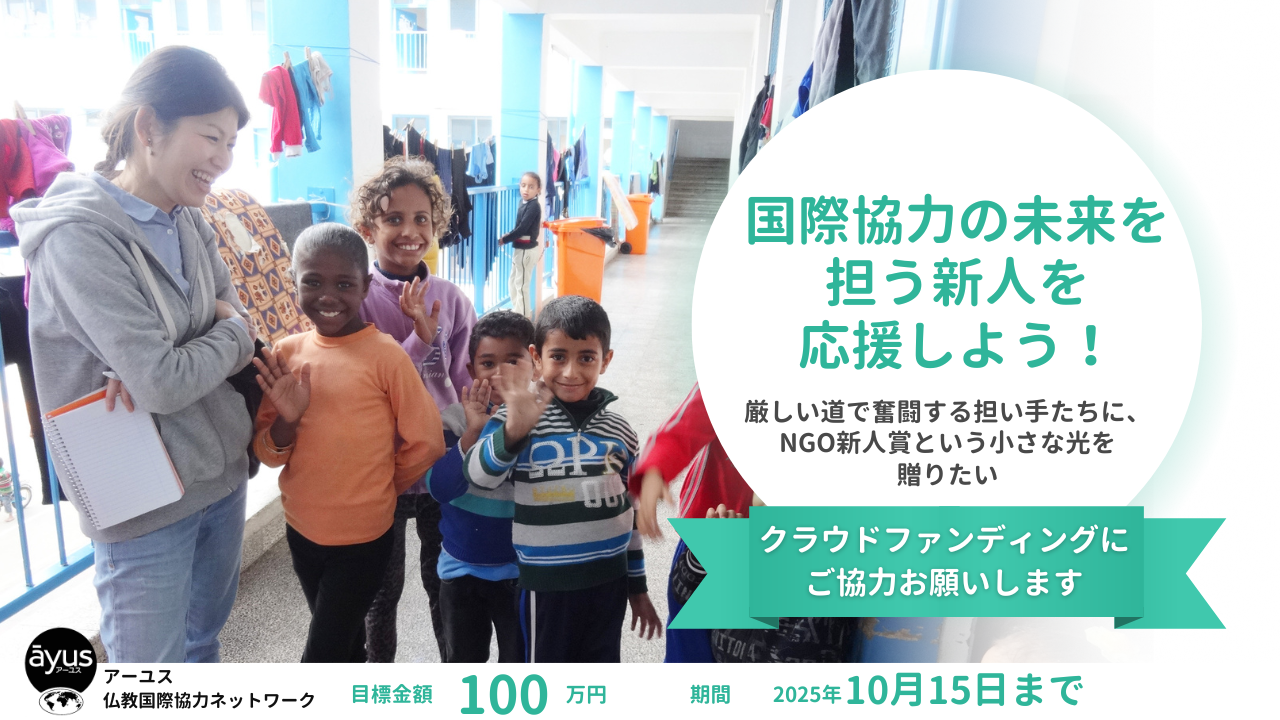日本の国際協力NGOをつなぐJANIC
枝木 まず国際協力NGOセンター(JANIC)のご紹介と、水澤さんの関わりについてお願いします。
水澤 JANICは日本の国際協力NGOのネットワーク組織です。いま日本に400から500の国際協力NGOがあるうちの125団体が加盟していて、企業や財団を含めると会員は200団体くらいです。
37年前の設立当時、NGOはばらばらに活動していました。NGO同士がつながれば、より効果的に市民とつながれたり、NGOセクターとして他のセクターと連携したり提言活動ができたりする。そうすることでNGOセクター全体が強くなると考えた。37年間、NGOの活動を推進するという根幹は変わらず、活動内容は時代に合わせて変化しています。
私自身はアドボカシー活動歴が長く、G7やC7※サミット、外務省やJICAとの協議会の事務局、最近ではNGOの組織力強化ということで注目を集めている「スフィアプロジェクト」(人道支援の国際基準)の普及などに従事してきました。
※「C7」は、G7各国の政府に対する働きかけをするグループのうち、市民社会で構成された「Civil7(C7)」のこと。
きっかけは2002年、大学院生のときにJANICの設立者の伊藤道雄さんと出会ったことです。ひとつのNGOではできないことをJANICはやるんだ、ということをおっしゃっていて、それがいいなと思ったんです。大学時代にフィリピンに留学したり、個別のNGOでボランティアしたりしたけれど、できることが限られていて、やってもやっても世界が変わらないという無力感があった。それでJANICに関わりはじめ、気付いたら事務局長になっていました。
枝木 JANICは様々なタイプの団体をつないで、現場でがんばっている団体が活動しやすくなるようにしてらっしゃいますね。
NGOの数は増えているのでしょうか?
水澤 小さな団体まで細かくは調査できていませんが、設立件数は1990年代、2000年代が多くて、2010年代からは減っています。いまはソーシャルベンチャーのように、NGOとは言わずに社会的にいいことをやっていこうという動きの方が盛り上がっているように感じています。
JANICの関係団体でも、社会的起業家を応援する団体や、国際協力に加え国内の課題に取り組むNGO/NPOやソーシャルベンチャー的な企業が加盟している団体もあり、会員数を伸ばしています。JANICもそれらの団体と一緒にアドボカシーをしたり、理事に入ってもらったりしています。
転換期にあるNGO
枝木 NGOもNGOを取り巻く環境も、変化していますね。
水澤 いま、すごい転換期だと思います。元気と勢いのあるNGOと、世代交代できなくて困っているNGOがある。世代交代は職員や理事だけでなく、支援者もそう。円安や物価高、少子化で採用難という状況もある。そういうなかでも元気な団体、財政を伸ばしている団体もある。
地域の団体に話を聞くと、リクルートどころか、そもそも地域に人がいない。リアルイベントは過疎化が進んでできない。かつては、NGOセクターが確立していなかったからこそ「これからやっていくぞ」というエネルギーがあった。今は難しい時代だと感じています。
枝木 JANIC自身はどうですか。
水澤 経営は大変です。受託や助成事業が多いのですが、受託単価は上がらない一方で人件費単価は上がり、採用は難しくなっていく。トランプ政権によって、アメリカの財団からの支援も受けにくくなってしまいました。JANICでは今年度の予算には影響ありませんでしたが、会員NGOの中にはアメリカの対外援助の大幅削減の影響で活動に支障をきたしている団体もあります。
枝木 そのほかにも、多様性の否定の風潮など、大変なことが多いですね。
水澤 JANICの会員NGOの中でも、多文化共生に取り組む団体はここ数年、とても増えています。そこに、外国の方に対する大きなご批判があり、NGOはいまこの課題にも直面しています。
わたしたちが大事にしている人権や、外国の方と共生する社会をつくっていくことなどについて、団体の垣根を越えてやるのがとても大事です。JANICにはワーキンググループという、NGO同士の学び合いや提言活動をともにしていく仕組みがあり、多文化共生ワーキンググループが2年前にできました。これからますますこうした連携、連帯が大事だと感じています。

ニーズに合わせて変化できるNGOへ
枝木 ところで、元気なNGOはなにか特徴はありますか?
水澤 現地や時代のニーズにあわせて変化していける団体は、伸びていると思います。
新しいトレンドとしては、インパクト投資ですね。海外ではNGOも行っていますが、日本ではまだまだ少なくて、インパクト投資をしている企業の方とはすごく溝がある。日本でも社会起業家などと連携していくことで、業界がもっと豊かになっていくと思います。
枝木 社会を変えていこうとする社会企業体に、NPOが投資するのが国際的なトレンドということでしょうか。日本ではまだ少ないですね。
水澤 先日ある国際会議に出たとき、NGOは物価高や円安で大変だということを切々と語っていた一方で、フィランソロピーや社会起業系の方々は「こういう新しいイニシアティブがある」といったお話をされていて、温度感が違います。
NGOも隣の業界のこと、新しいことを学ぶのは大事です。
新しい世代とともに
枝木 若い世代はNGOより社会的起業のほうに関心が高いのでしょうか。
水澤 JANICは今年新人を2名採用していますし、今年、グローバルフェスタで、社会課題解決のアイデアを募集する「学生アイデアコンテスト」を実施した際には学生から質の高い応募が100件以上ありました。社会課題に対する関心がないわけではない。NGOセクターが魅力的であれば、少子化であっても若い方も来るはずだと思います。リクルートがうまいNGOもありますよね。外部要因だけではなく、わたしたちも努力する必要があります。ただ昔と比べて求人への応募は減ってはいます。
枝木 NGOは給与が低い割に能力を求めすぎるきらいがありますね。こちらの魅力がない、見せられてないということでしょうね。
水澤 「選ばれる」NGOセクターでありたいです。
JANICは理事の世代交代ができていて、30歳前後の理事もいます。新しい世代としっかり一緒にやっていくことが必要です。
枝木 理事会の雰囲気は大きく変わりましたか?
水澤 だいぶ変わりました。かつてはみんながわあっと議論していたのが、前理事長が理事会などでワークショップを始めいろんな手法を取り入れた。そうした新しい世代のもつノウハウをシニア理事が受け入れて、楽しみながら新しい手法にトライしたのが理事会の変革のひとつと思います。そのため、若い理事も発言しやすいのではないかと思います。
NGOだからできること
枝木 転換期にあっても、NGOならではの魅力、他セクターではできないことは何だと思いますか。
水澤 現場をもつNGOであれば、NGOだからこそ寄り添える、深いところまで見える、人と人の心を大切にする支援が得意ですよね。新しい援助の潮流を試せる柔軟性もある。行政などはやり方を変えるのも大変です。それから、現地の人たちと一緒にやりたいことをやれる。現地の方々と一緒につくりあげる喜びが、NGOならではと思います。
政府へのアドボカシーも、市民セクターだからできること。行政のなかにいては見えない課題や、現場で本当に必要なことを提言するのが、JANICの役割だと思っています。
枝木 JANICのアドボカシーは、NGOからの要望に応えて声をまとめているのでしょうか。
水澤 会員NGO主体のアドボカシーをサポートする形もあれば、JANIC主導のときもあります。賛同や拡散という形で応援させていただいたり、大きな国際会議のときは、日本のNGOの意見をJANICがとりまとめて提出するという役割を果たしました。
地域や市民とつながってこそ
枝木 その際はNGOだけでなく市民全体にアプローチをしているのでしょうか。
水澤 そこは課題です。NGOの提言内容はすごく専門的で、それをわかりやすく解説するのは苦手。それでは市民はついてきません。核廃絶や債務帳消しの運動は、市民を巻き込むことで大きな運動になり、政府も動かした。市民にどう共感してもらうかがカギです。
2023年のひろしまサミットでは、広島の市民サミットという形で、現地で市民の方々とイベントをしました。広島は現地のNGO・NPOがもともと熱心に活動していたのも大きいです。次の日本でのG7サミットはおそらく2030年になると思いますが、今回できたネットワークをそれまできちんとつないでいきたいです。
枝木 NGOの国内の運動は省庁のある首都圏に偏りがちですが、サミットでは広島など各地域の市民団体とつながる良い機会ですね。
水澤 いかに地域に根差した活動をしていくか、市民と一緒に活動していくかが大切で、それがないとNGOは市民セクターとも言えないと思います。
NGO職員に求められる資質とは?
枝木 NGOで働くことの難しさとは何でしょうか。
水澤 NGOは大変な現場を見ることが多いです。海外だけでなく国内もそう。そこを見ることのできる強さ、そこを乗り越えていける強さは必要かなといつも思っています。お金もない、人も少ないとなると、「私ががんばらなければ!」となりがち。それではバーンアウトしてしまう。自分をコントロールしてやっていく強さも必要だと思います。
枝木 JANICやアーユスのように、後方から応援する立場のNGOについてはどうでしょう。
水澤 JANICはいろんな団体を調整しなければならない大変さがあります。コーディネート力がとても求められている。現場で活動するNGOも、ドナーや受益者、支援者などいろんな方と調整していく力が必要ですね。
NGOにもメンタルケアを
枝木 ときには精神的に滅入ってしまうことも起こりがちです。
水澤 JANICの最近の研修ではメンタルヘルスをテーマにしたり、組織内でストレスチェックを導入したり、産業医制度を設けたりしています。各団体にアンケートをとると、NGOの経営責任者からメンタルケアが課題として挙がり、研修をやってほしいとか、JANICはどう対応しているか教えてほしいといった声がここ5,6年増えている気がします。
スタッフが健康に働けるように、心身の管理が重要だということを、NGOの経営者には自覚し、対応してもらいたいです。
枝木 アーユスも気を付けなくてはいけないと思っています。
NGOではいろんなことにセンシティブでなくてはいけないと同時に、多少の鈍感力も必要なように思います。
水澤 NGOは真面目な方が多いので、真剣にそれぞれのことに向き合う。負荷が大きいですから、リラックスする時間や思いを語り合う時間をもつのも必要ですし、時間がかかっても一人ひとりの思いと向き合うのが大事だと思います。
活動家魂と、コンプライアンスと
枝木 最近はオン/オフの切り替えを大切にしようという傾向がありますね。昔のNGOはオンオフ関係ない、24時間活動家だ、というところがあった。最近はどうでしょう。
水澤 かつては、JANICも大きなイベントのときは24時間頑張ります!という感じだった。最近は、残業時間もきちんと管理して、コンプライアンスを守ってとか、ボランティアさんをお願いするなら保険に入って、など細かく考えます。そういうところが20年前と変わっています。
とはいえ、活動家魂を失っているわけではなく、社会的コンプライアンスとのバランスに苦労しているところです。
枝木 その点でも転換期ですね。活動家魂を失いたくないが、やりがい搾取になってもいけない。職員も自己実現したいことがあるはず。マネジメントとして、スタッフのどの部分をどう伸ばすかは、悩ましいです。
水澤 その方を大切にすることを考えていれば、そんなに間違ったことにはならないと思います。あとは、法律を守ること。
でもわたしたちはやはり活動家で、NGOは運動体。プライベートの時間でも世界情勢に目を配る、ふだんから仲間との時間を大切にする、ボランティアさんたちともしっかりコミュニケーションする、そういうことも大事です。
枝木 最後に、次の世代やNGOの新人さんにメッセージをお願いします。
水澤 まず、NGOに関心を持ってくれたこと、このセクターに入ってきてくれたことが嬉しいです。社会課題を何とかしたいという思いがあることが貴重。その思いを大事に活動していっていただきたいと思います。
枝木 わたしたちも組織を運営する立場として、それぞれの思いをちゃんと受け止めながら、それを形にできるようお手伝いをしていきたいです。
今日は励まされるお話をありがとうございました。
(2025年10月1日)
金額3,000円 |
金額5,000円 |
金額10,000円 |
金額50,000円 |
金額100,000円 |
金額3,000円 |
金額5,000円 |
金額10,000円 |
金額50,000円 |
金額100,000円 |