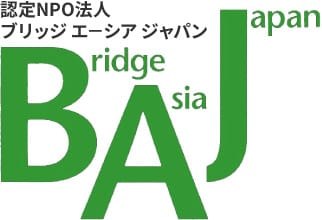拝啓 いつもミャンマーを気にかけてくださる皆さま
「積み上げてきた希望そのものが瓦礫と化した瞬間だった」
昨日、紹介した現地スタッフの言葉です。
考えてみれば、これまでも活動が無に帰すような状況は何度かありました。
いちばん思い出されるのは、「ロヒンギャ危機」あるいは「ロヒンギャ難民危機」として知られる大量難民が発生した2017年8月です。正直、いまも心の整理がついていません。思い出したくもないのが本音です。現場にいなかった私でさえ、そんな状態です。あるいは現場にいなかったからこその反応なのかもしれませんが(…もうすでに混乱しています)
幸運なことに、当団体職員が命を落とすことはありませんでした。しかし、現地スタッフの少なくない人数がバングラディッシュに逃れて難民になりました。
いま、バングラディッシュの難民キャンプでは、当時難民となって出ていった元BAJ職員たちがNGOのスタッフとなって活躍していると聞いています。頼もしいし、誇らしいと感じます。ですが、無力感や申し訳なさが、同時にその感情の裏側に張り付いています。現地スタッフだけでなく、当時駐在していた日本人スタッフも命からがら脱出しました。
*
大量難民発生の一週間前、私はちょうどマウンドーにいました。私にとって初めてのラカイン州北部への出張でした。
ここがBAJのミャンマーの活動がはじまった出発点の事務所。――
あのころ、ミャンマー国内に複数の現地事務所がありましたが、マウンドー事務所の雰囲気は特別なものがありました。
ラカイン、ビルマ、チン、カレン、そしてムスリム。さまざまな民族の背景を持った仲間たちが、いっしょに汗を流して働いていました。
空気がよい意味で張り詰めていて、みなが誇りを持って仕事をしていました。私たちにしかできないことをやっているという自信にみなぎり、地域の未来のために働こうという気概に満ちあふれていました。背筋が伸びる思いでした。
さわやかでピリッとした組織風土。長年にわたる国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)とのパートナーシップが事務所を成長させたのはもちろんですが、このとき駐在していた若い日本人マネージャーのプロフェッショナルな仕事ぶりと情熱も大きな要因だと思います。
この世界の矛盾と複雑さが一点に集まったような辺境の地で、タフな交渉をしながら、切磋琢磨して、国連機関、ミャンマー政府、村落住民、いろいろな人たちと信頼関係を築いてきたからこそ、この空気感が創られました。
ちなみに「ムスリム」は「ロヒンギャ」のことです。当時も今も「ロヒンギャ」という言葉には政治的な鋭さがあります(少なくとも私たちにとっては)。言葉はじつに厄介で、使われる場所、それを受け取る人たちによって意味が大きく異なっていきます。極端なことをいえば、家族で話す言葉と、会社で話す言葉は、ぜんぜん違います。あいつと話すときの言葉と、あの人と話す言葉は、同じだけど同じじゃありません。
そのため、思わぬ対立に巻き込まれて活動に支障が出ないよう、現地で好んで使うことはありませんでした。そして、それは遠く離れた日本の東京事務所でも同じで、東京で発信した内容が、現地職員を危険に晒すことを避けるため、これまで「ロヒンギャ」という言葉はあえて使わずにやってきました。
少し皮肉なことかもしれませんが、2017年に「ロヒンギャ危機」が世界中でニュースになった影響で、そうした言葉の繊細な政治的対立はどこかへふっ飛んだような印象があります。その頃から私たちもおそるおそる「ロヒンギャ」という言葉を便宜的に使うようになりました。しかしながら、ラカイン州の現地ではいまも「ムスリム」です。
*
東京事務所のホワイトボードの黒いつまみには、ラミネートが紐で引っ掛けてあって、いつでも紹介できるようにぶら下がっています。2017年7月某日のミャンマー国営紙の一面の記事です。UNHCRの高等弁務官がBAJの活動現場を訪れたときの様子が写真とともにレポートされています。
マウンドー事務所敷地内に設けた教室で、ラカインとムスリムとその他少数民族の女性たちが裁縫技術を学んでいます。平和的共存事業と名付けてUNHCRの資金で行なった活動でした。記事は、具体的な民族への言及は避けつつ、コミュニティ間の平和的共存や信頼構築について淡々と説明していました。
いよいよ状況が変わるのかもしれないと思いました。大量難民発生の「危機」が起こるおよそ1か月前の新聞でした。
「積み上げてきた希望そのものが瓦礫と化した瞬間だった」
それでも、2017年の危機から5年が経って、なんとか裁縫教室を再開することができました。まだ働く場所と仲間たちがいたからです。そして、現在は廃墟がそこにあるだけです。
募金キャンペーンに「あきらめない未来」と掲げていますが、私たちの希望の未来はすでに過去にあったと思っています。ささやかだけど、みなといっしょにつくった未来が、かつてそこにあったのです。私はそれを今こそ大きな声でいいたい気持ちです。
再び立ち上がれるときを信じて、過去にあった未来の希望を見つめています。
皆さまのご支援にあらためて厚く感謝申し上げます。

このときの高等弁務官の訪問はUNHCRが動画を作成しています。以下ご参照ください。当時、私たちが感じていた希望が少しでも伝わったらうれしいです。