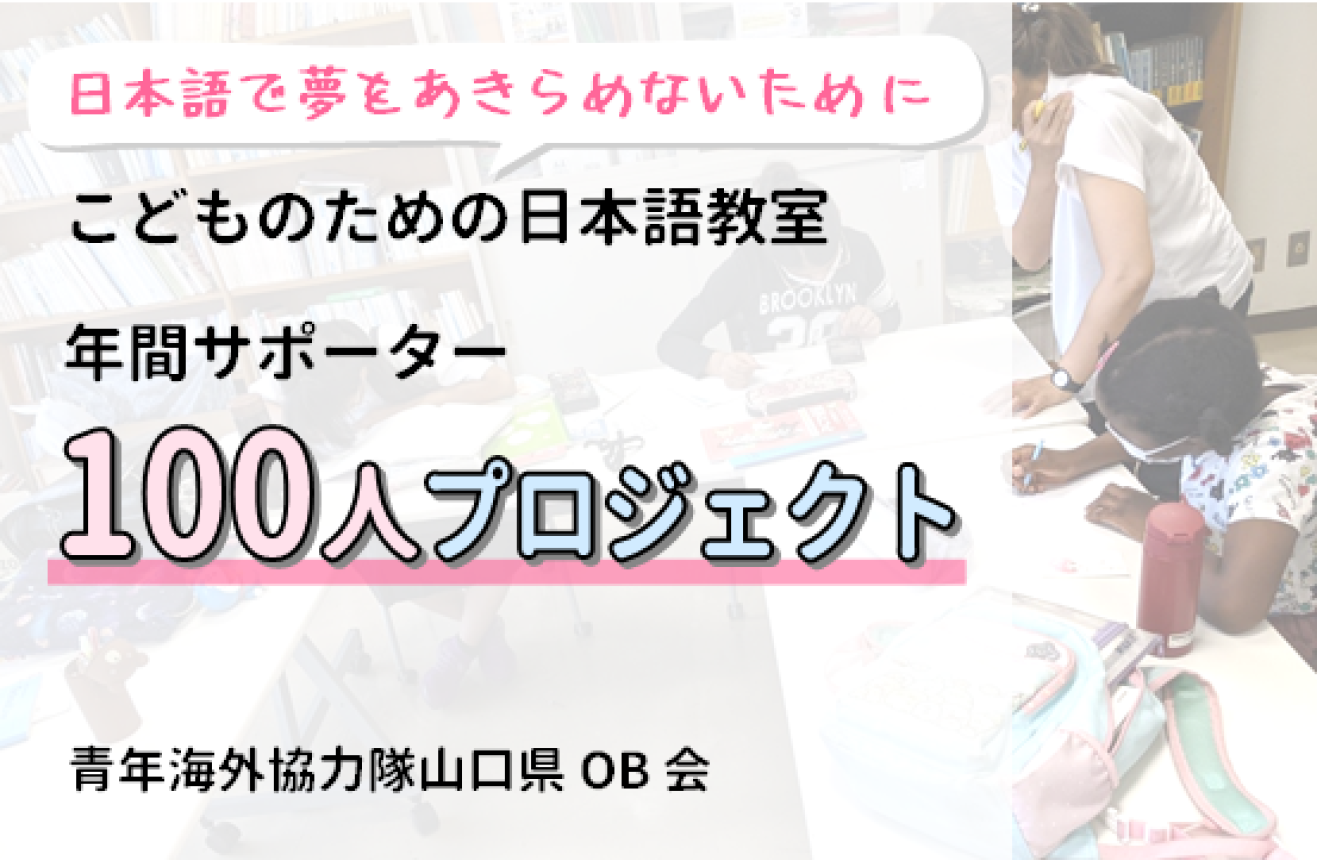学校の中で1時間目から6時間目まで、ずっと分からない言葉を聞き続けることは、どんなに苦痛だろうかと思います。
周りの子ども達は楽しそうに笑っていて、でもその笑いの意味すらわからない。
家族も仕事で忙しいからと、そんな気持ちをゆっくり聞いてくれる時間の余裕もない。
そんな状況にいる外国ルーツの子ども達のさびしさを思うと、なんとかしたいと切実に思います。
そして、国語の長い文章を読もうと促すと「いやー」と言われたり、
算数の文章問題を「めんどくさい」と言われたり、
分からない理由を知りたくて、どこが分からない?と聞くと、さらに「分からない」と答えられたり、
日本語教室の場でこんな反応が返ってくると、日本語の難しさと直面しているんだなと感じます。
日常会話で使われる「生活言語能力」と、勉強などの場面で使われる「学習言語能力」
その習得には、生活言語能力は2年程度、学習言語能力では5~7年程度かかると言われています。
思考は言語によって認識されており、言語化されていないものは、あいまいにしか認識することができません。
もやもやとした感情に名前を付けるためにも、そのための言語が必要になります。
「さびしい」という言葉で表現できるようになっても、その奥にはもっと細やかな感情があるはずです。
それらは少しずつ違う言葉で表現することができます。
母語と日本語、その両方を行き来する子ども達の成長過程を見ていると、その言語が広く深く育っていっているだろうかと不安になります。
つたない表現の奥にあるもの、それを丁寧に聞くこと。
そして、それを表現する言葉を手にすること。
その両輪を担える存在が必要だと思っています。
今、私たちの教室の中では、それが少しずつ形になってきているのではないかと感じています。
それがあたり前にある社会になるまで、私たちのできることを頑張っていきたいと思います。
青年海外協力隊山口県OB会
副会長 松浦 和子